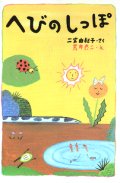 『へびのしっぽ』(二宮由紀子作 荒井良二絵 草土文化社 1200円)に挿入されていた、評者向けの編集者の文面を引用することから、世紀末とやらを始めたい。
『へびのしっぽ』(二宮由紀子作 荒井良二絵 草土文化社 1200円)に挿入されていた、評者向けの編集者の文面を引用することから、世紀末とやらを始めたい。「このたび弊社では、創作児童文学『へびのしっぽ』を低学年向きに刊行いたしました。こんなおはなしです。へびのしっぽは、たいくつでした。まえが、ぜんぜん進まないからです。いつも頭任せで、ずるずると引きずられていくしかないへびのしっぽは、せっかく出会った人たちとおともだちになろうと思っても、うまくいきません。だって、勇気を出して「ともだちになってください」っていうたびに、ずるずる引きずられていってしまうものだから…。そんな“しっぽ”であるがためのジレンマをユーモアたっぷりに描きます」(田中恒)。
この事態はジレンマではないが、仮にそうだとして、これは、「ジレンマ」を「低学年向き」に描いた作品であるという説明となる。一方書物の帯を見ると表には「そうか、もんだいは たちどまりたいときに とまれないことなんだ」とあり、背は「たちどまればいんだ」で、裏には、「自分の進路を他人任せにしたり、何をやるにも自信がもてない人たちの象徴のような“へびのしっぽ”。しかし消極的な人でも、きっかけさえあれば新しい一歩が踏み出せる、そんな勇気を与えてくれる癒しの児童文学」とある。
つまり、商品として書店にある『へびのしっぽ』の帯からのメッセージは、裏に関してははっきりと大人のための癒しの児童文学であることを表明している。もっとも、評者への文面に「幼児から大人まで、読み手の対象によって変化する、とてもおもしろい文学だと思います」とあるし、私も同意するが、そのための大人へ向けてのキャッチが「癒し」であるところに、児童文学の「ジレンマ」が浮上しているのやね。
さて、癒しなんぞはさっぱり忘れて『へびのしっぽ』へ帰ってみよう。まずしっぽは退屈している。前がちっとも進んでくれないから。自分の意志で動ける頭はいいな、それにくらべてしっぽは頭任せ。しっぽは頭を尊敬しているのに、頭はしっぽのあることなんか忘れているようで、振り向いてもくれない。誰もしっぽを気にしてくれない。仕方なくしっぽは前を見るのをやめて横に咲いているタンポポに話しかける。「こんにちは、ぼくへびのしっぽです」。と、ちょうどそのとき頭は進みだし、しっぽの挨拶はタンポポではなくスカンポに聞かれてしまう。それでしっぽはスカンポに「ぼく、あなたと、おともだちになりたいな」と言うけれどやはりそのとき頭が進みだし、その言葉はイヌのウンコに伝わる。仕方なくしっぽはウンコと会話しようとするのやけれど・・・と、続いていく。
つまり、しっぽのメッセージは彼の望む送り先には決して届くことはなく、常に誤配されることとなる。ただし誤配とは、誰かには確実に届くという意味でもある。従ってしっぽはズレながらも、彼の存在を示していくことができている。「『こんにちは、ぼくへびのしっぽです』とスカンポに言ったと誤解される存在」。「『ぼく、あなたと、おともだちになりたいな』とイヌのウンコに言ったと誤解される存在」という風に。
が、帯のコピー通り、最後にしっぽは「たちどまればいんだ」と気づき、頭の意向を無視して、テントウムシと話すために立ち止まる。初めて彼のメッセージは誤配されない。と、急に止まったことに驚いた頭が「お。だれがとまったんだい」という。嬉しくなったしっぽは叫ぶ。「ぼく!」。当然のことながら、この瞬間しっぽは、意志のレベルに於いては頭とは切断され独立した存在であることから「へびのしっぽ」へと位置づけを変えられてしまう。
つまり、しっぽであるがためにメッセージが誤配されることがジレンマなのではなく、誤配されることで得られる「存在」か、誤配がなくなることによる「存在」の消失か、この決定しがたい事態がジレンマなのやね。そしてそれが、「子ども観」と子どもを巡るジレンマに重なるのは言うまでもない。
読書人99.01.22