![]()
No.82 2004.10.25日号
|
【絵本】 ○今時の韓流絵本  「あかいきしゃ〜はじめてであうハングルの絵本」パク・ウニョン絵と文 おおたけきよみ訳(アートン 1997/2004.8) 「パパといっしょに」イ・サンクォン文 ハン・ビョンホ絵 おおたけきよみ訳(アートン 2003/2004.9) 「わたしの社稜洞」キム・イネ文 ハン・ソンオク絵 おおたけきよみ訳(アートン 2003/2004.10) 毎月1冊刊行をされているアートンの「韓国の絵本10選」。前期の5冊は韓国絵本のロングセラーの中から選ばれてきたが、後期になって最新の絵本を同時期に日本でも手にとれるようになった。この三冊はどれも印象が違って見える。 韓国のあいうえお、といわれるハングルと日本語訳との並記がめずらしい「あかいきしゃ」。文字の違い、音の違いが不思議で楽しい。でも、小さな子どものための絵本としてのつくりは、とてもオーソドックス。汽車をシンプルで力強いイラストで表現し、どんどん進んでいって、ページごとに風景が変わる展開。汽車に載せた星や月を夜空に運んでいくというサブストーリーを絵だけで見せる、などテキストだけではなく、絵でも語らせて奥行きのある絵本に仕立てている。 現代韓国絵本の人気画家ハン・ビョンホの新作「パパといっしょに」は今まで紹介された絵本とは、また違ったタッチのイラストで、軽やかでかわいらしい。自身も女の子を持つというビョンホが楽しそうに秋の中の父子を描いている。二人のセリフだけで展開するこの絵本は、映画のようで、引いたり寄ったり、カメラワークも自在な感じ。余白の多いイラストが気持ち良く、ラストシーンの山頂からの風景で、ソウルの今を強調しているのがわかった。 今のソウルを象徴するのが「わたしの社稜洞」に見られる古い町並みの解体である。この絵本の特徴はアートディレクターでもある画家が、自ら暮らした町の写真を元に実在の町の変遷を絵本化したところ。写真を元にしたイラストは、日本でも広告イラストレーションや書籍の挿画などで良く使われるが、子どものものとして提出されるのはあまり見たことがない。写真を構成した写真絵本とも違った不思議な味わいのある絵で、このテキストにはぴったりである。それも、まず、町の写真やテーマなどを画家が作家に提供し、共同で作業していったからにほかならない。写真そのままでは実際のノンフィクションとして、ある国のある限定された土地のお話として、そういうことがあったのね、とすませてしまいがちであるが、丹念にトレースされ、淡い色彩で彩られた絵は、実在のものでありながら、誰もの心の中にある古い記憶へとつながっていく。 最近の韓国絵本は新しいイラストレーターの輩出や国際児童図書展などでの受賞など、元気がいい。ただ、私見ではあるが、絵やストーリーの着目はいいのに、ラストのまとめが弱かったり、子どもの気持ちを開放する、というよりは、教化することに意識が高かったり、まだまだだなと思う本も多い。ただ、出版物として、いろんな手法のイラストやテーマに挑んでいる(民族の風習や故事などを今の作家で今の子どもたちに伝えようとするシリーズなど)ところ、新しい出版社が企画やコンセプトを強く打ち出して、画家や作家と共に新しい韓国の絵本を作っていこうとしている姿勢がいいし、これからを期待させる。 ○その他の絵本、読み物 「おへやのなかの おとのほん」マーガレット・ワイズブラウン文 レナード・ワイズガード絵 江國香織訳(ほるぷ出版 1942/2004.9) ワイズブラウンのNOISY BOOKシリーズの中の1冊。このシリーズはワイズブラウンが大学で学んだ幼児へのアプローチの仕方をそのままテキストの視点に持ち込んだものとして評価の高い絵本である。季節で作ったり、場所で作ったりしているが、シリーズで出ていることからもわかるように、視覚表現の媒体であると考えられがちな絵本で、あえて音に注目したコンセプトが、今も古びていないところがおもしろい。ワイズブラウンは絵本を声(音)を介して表現されるべきものとして創作を行っていたのだろう。イラストは今見るとレトロすぎて、小さな子には抽象的すぎるのかな、とも思ったが、はっきりとしたコントラストで強さはある。声に出して読んでみて、繰り返しややり取りの楽しさが思った以上であったこと。お部屋の中という自分の身近なところを舞台にしてること。ワイズブラウンらしい、ちょっととっぴょうしもない取り合わせが子どもの優越感をくすぐるところなど、いっしょに読んでいて楽しかった。 「魔女の子どもたち」アーシュラ・ジョーンズ文 ラッセル・エイト絵 三原 泉訳(あすなろ書房 2001/2004.9) 魔女の子どもが親のいぬ間に魔法を使って、とっても大変なことになってしまう!という絵本は魔女ものの一つのパターンになってはいる。この絵本もおにいちゃん、お姉ちゃんの使った魔法がとけなくて、もう、どうすんのよお!とおこらてしまった時、末っ子がただ一つ使える魔法でことなきをえました、というお話。イラストがデザインがかっているけれども愛らしく、リズムがあって今風。かあさん魔女の造型もなかなかたくましく、楽しかった。 以上、ほそえ。 --------------------------------------------------------  『いのり』(フィリモン・スタージス文 ジャイルズ・ラロッシュ絵 さくまゆみこ訳 光村教育図書 2000/2004.09 1800円) 『いのり』(フィリモン・スタージス文 ジャイルズ・ラロッシュ絵 さくまゆみこ訳 光村教育図書 2000/2004.09 1800円)ペーパークラフトの優しげでぬくもりのある画がまず印象的。 様々な宗教の聖なる祈りの場所が切り取られ、画面に置かれているわけだけど、そうした技法そのものが、画全体に静謐感を与えている。 世界中の宗教が集うこの絵本は、今一番必要な場面を描いている。(hico) 『絵本ジャンヌ・ダルク伝』(ジョセフィーン・プール文 アンジェラ・バレット絵 片岡しのぶ訳 あすなろ書房 1998/2004.10 1500円) 物語はおなじみのもの。無駄なくまとめられていて、まだ知らない子ども読者へのいい情報です。 もう、画がいいったら。 表情から背景の隅々まで、描き手の心が伝わってくる。 巧いというのではなく、あ、巧いのですが、それより何より、綺麗でいて臨場感あふれるタッチがなんとも。ドキドキです。(hico) 【創作】  『アグリーガール』(ジョイス・キャロル・オーツ:著 神戸万知:訳 理論社 2002/2004.05) 『アグリーガール』(ジョイス・キャロル・オーツ:著 神戸万知:訳 理論社 2002/2004.05)原題は、Big Mouth & Ugly Girl。コラムや戯曲を書く「ビッグマウス(=大口たたき)」のマット・ドナヒーが、自分の通う高校の爆破予告をしたという嫌疑をかけられる場面から話がはじまる。容疑はやがて晴れるものの、<普通>の人気者だったマットが、周囲の悪意にはまりこんでいくのを読むのがつらかった。濡れ衣での逮捕のときよりも、訴訟を起こした後の周囲の反応の描かれ方に、なるほどと思う。リンチやパンプキン誘拐も、胸が痛くなった。男の子の誇りが傷つけられる痛みが感じられる。 アーシュラ(=アグリーガール/自称)に感情移入してみると、せつなくおもしろくじーんとなり、ラストも味わいがあった。友情が愛情に変わるのだけど、このくらいの年代のときって、「何より大事」の一途な気持ちが同性に向いたり異性に向いたりして、その相手と親友にも恋人にもなれるのだ。 アーシュラのような高校生がフィクションできちんと描かれていることがうれしい。現実には、こんなに強く冷静に、パッションを秘めて凛としていることはできないかもしれないけれど、そのモデルが本の中にいることは、10代の読者には大事なことではないか。強いアーシュラがリサに見せるちょっと複雑な妹思いの気持ちや、親への苛立ちとでも「求める」心、鋭さゆえの感受性の豊かさもよく描けていて、とても印象深い。 (鈴木宏枝) 『チョコレート・アンダーグラウンド』(アレックス・シアラー:著 金原瑞人:訳 求龍堂 2003/2004.06) チョコレートという、ちょっぴり魅惑的でちょっぴり背徳的で、だけど人生のスパイスの<甘さ>をくれるものをモチーフに、自由と弾圧のアレゴリーを近未来的に描いている。 健全健康党が支配してしまった某国では、砂糖もチョコレートも健康に悪い甘味も禁止になってしまった。チョコレート大好きで反骨精神のあるハントリーとスマッジャーの二人組の少年は、仲良しの駄菓子屋のバビおばさん、古本屋のブレイズさんらと、チョコレートの密造と<地下チョコバー>というもぐりのチョコレート愛好の場をつくる。 笑いながらもどこか笑えないのは、イギリスの状況は肌では分からないが、今、日本でなんだか同じ空気があるように感じてしまうから。一方で、途中で、チョコレートがすごく食べたくなってしまって、久々にミニサイズのチョコを買ってしまう。 フランキー少年の事情と、彼が制服を着て少年団になったときにすごく「らしさ」を発揮することや、ハントリーのママが、くすねてきた隊員の制服を着たときに「ミニ・ヒトラーになった気分」と言う場面などから、制服がひとをつくることを思った。 どういう制服を着ると、チョコレートを禁止し、<健全健康>第一を信奉するようになるのか。その制服は、今、私にも、すぐ手の届くところにあり、時には着ることもあるかもしれない。制服によって簡単に体制側になりえてしまう怖さを感じてしまった。また、反抗することが、こんなにコミカルにではなくナチスがやったような死を意味するとき、私は本当に反骨精神が持てるだろうか。 (鈴木宏枝) 『真夜中の飛行』(リタ・マーフィー:作 三辺律子:訳 小峰書店 2000/2004.08) 訳者の後書きによると、作者は、「ハンセン家の女たちは、どんなに天気が悪くても、かならず夜に飛ぶ」という着想からこの物語を書いたという。今回、なんとなくこの後書きを先に見てから本文を読んだら、ちょっと予想と違っていた。魔女的なファンタジーではなく、少女のイニシエーションと家族の変容が、魔法や超現実の要素の出てこないリアリスティックな作品以上に鮮やかに描かれている。 ハンセン家は、屋敷で3代が一緒に暮らしているが、おばあさまの言い渡した「敷地内に男は住むべからず」の決まりどおり、男はいない。主人公のジョージア、母親のメイヴとその姉妹(ジョージアの叔母たち)のエヴァとスキ、おばあさまのマイラ。彼女たちを結ぶ血筋は「飛べる」家系であること。ファンタジーらしいのはこの一点だけなのだが、その「飛ぶ」感覚も、風の冷たさや飛翔の高揚感、方向を定めたり着地したりするときの緊張など、ものすごくリアルで、飛んだことがなくても、こんな感じなんだろうな、あるいは、こんな風に飛ぶひとっていそうだな、と思えてしまう。 おばあさまの力が圧倒的に強い屋敷の中で、ジョージアの16歳のイニシエーション(「単独飛行(ソロ)」をめぐり、母の世代とジョージアとが、おばあさまからいかに自由になるか。ジョージアにとっての特別な日は、家族みんなにとっても、特別な日になった。 長い間屋敷から離れていたカルメンの造形がいい(名前も示唆的である)。叔母たちそれぞれの優しさとあたたかさも、しっかり感じる(っていうか、家系図によると、私はもうこの世代なのだった…)。 (鈴木宏枝) 『人形の家』(ルーマ・ゴッテン:作 瀬田貞二:訳 岩波少年文庫 1947/1968) 『人形の家』は、二つの視点から描かれています。主人公をトチーとする人形たちと、人形で遊ぶエミリーとシャーロット姉妹の視点です。姉妹には人形たちの声が聞こえませんが、人形たちは姉妹の話を理解しています。姉妹は人形たちでごっこ遊びをするのですが、人形の気持ちはわかりません。一方人形たちは人間の気持ちは理解できるのですが、自分たちの思うように事を運ぶことはできません。トチーの言葉を借りれば「願うことができる」だけです。とても歯がゆい事。 ファンタジーには様々な描き方がありますが、何故ファンタジーである必要があるのか? この問いへの答は多くの場合似ています。 日常のルールを越えないことには描けないテーマだから、というのがそれです。例えば『ゲド戦記』は、魔法で自分の影を解き放ってしまった若者ゲドが、その影と向き合い再統合する物語。極めて抽象度の高いテーマです。が、魔法が存在する世界なら、その魔法によって、自分の影を解き放ってしまうという設定も、あり得そうです。 この物語では、人形が人間のように話をします。そうしなければ描けないこととは何か? とても歯がゆい事? それもあります。しかし、それだけならファンタジー仕立てにしなくとも描けます。主人公が子どもであれば、大人社会で自分の意志が通らない、とても歯がゆい事を経験する物語はいくらでもあります。人形物語の人形は、子どもをシンボライズしているとの見方もあります。読者の身に降りかかっている問題を人形に仮託させ、少し距離を置いて、眺められるようにするというわけです。いつもそうでしょうか? というのは、『人形の家』で言えば、トチーたちを自由に操れるのは子どもたちだからです。子どもはトチーたちの視点で読むのでしょうが、人形を時に理不尽に扱うのは、読者と同じ子どもなのです。もし読者が人形遊びの経験があるなら、トチーたちの運命に心を痛めながら、自分の遊び方を反芻するでしょう。人形の視点から、自分も含めた子どもを眺めることになるわけです。 そして『人形の家』の場合、百年生きているトチーは、子どもをよく知っていて、「どんなことがあったって、子どもにはなりたくないわ。」と述べます。人形の視点に立って読んでいる子どもが、同時に人形によって批評されるのです。これは何とも不思議な読書体験になります。 もう一つは、奇妙な家族構成です。実はこの人形一家の娘であるはずのトチーは、人形たちの中では一番古株なのです。彼女は、自分が知っていることを親に教えます。人間世界で子どもたちが体験している、親と子、大人と子どもの力関係が存在しない家族です。子ども読者が、その心地よさを味わってみるのも悪くはありません。 それは人形物語だからこそ成立しているのです。(hico) 徳間書店「子どもの本便り」2004.08〜09 ------------------------------------------------------------  自分はどういうキャラだとか、自分たち中学生は社会でどんな立場にいるかだとかを判ってしまっているコは今、結構いると思う。『バラ色の怪物』(笹生陽子 講談社 千三百円)に出てくる遠藤トモユキもそんな一人。判っているから、そこからはみ出すことはしたくない。だって危険度が高すぎる。でも判っている日々が退屈なのも確か。そんなトモユキの前に一つ年上の三上が現れ、「中学生って、つまんないよね。なにもかも中途半端でさ」と言い切る。彼はレアカードをネットで売買する組織を運営していて、トモユキはボディガードに雇われる。中学生からはみ出し、判らない世界に足を踏み入れるけれど・・・。 自分はどういうキャラだとか、自分たち中学生は社会でどんな立場にいるかだとかを判ってしまっているコは今、結構いると思う。『バラ色の怪物』(笹生陽子 講談社 千三百円)に出てくる遠藤トモユキもそんな一人。判っているから、そこからはみ出すことはしたくない。だって危険度が高すぎる。でも判っている日々が退屈なのも確か。そんなトモユキの前に一つ年上の三上が現れ、「中学生って、つまんないよね。なにもかも中途半端でさ」と言い切る。彼はレアカードをネットで売買する組織を運営していて、トモユキはボディガードに雇われる。中学生からはみ出し、判らない世界に足を踏み入れるけれど・・・。一方、小さい頃から好きだった人(今は大学生)にラブレターではなくお誕生日カードを出しただけで、恥ずかしくて仕方がないつばめもまた、「中学生って(略)ちゅうとはんぱな年齢だ」、と思っている。『宇宙でいちばんあかるい屋根』(野中ともそ ポプラ社 千二百円)はそんな彼女の心の動きを丹念に追う。つばめを支えてくれるのは、不思議な年寄りの星ばあ。キックボードに乗り、住所不定。自分を判ってしまっているつばめは、怒られるようなことはしないし、他人を傷つける言葉は口にしないのだけれど、星ばあはそんな彼女を挑発する。 判っていると思い込んでしまっている十四歳へのメッセージ。 読売新聞2004.10.18 ---------------------------------------------------------------- 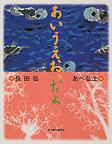 この本はむつかしいなあ。いや、内容じゃなくて、紹介がむつかしいんだ。そもそもタイトルが『あいうえお、だよ』(作・長田弘、絵・あべ弘士、角川春樹事務所、1400円)だよ。 この本はむつかしいなあ。いや、内容じゃなくて、紹介がむつかしいんだ。そもそもタイトルが『あいうえお、だよ』(作・長田弘、絵・あべ弘士、角川春樹事務所、1400円)だよ。どんな話かというと、「あといとうとえとお」の「5つのことば」が世界を作る話……なんか、よけいにむつかしくなってきた? だけど、ちっともむつかしくはない。 どうなるかというと、「あ」は木になって、「い」は鳥になって、「う」はみずうみになって、「え」は風になって、「お」は星になる。それからみんな、冬になったり、雨になったりする。 次はそれぞれ、色になったり、線になったり、ゴリラになったり、一角獣になったりして、最後は「か」や「き」や「く」や、そのほかのみんなを呼び集めるわけ。 こうして「世界」ができあがる。 どうやら、この絵本は、世界の作り方の本らしい。そう、世界を作ったのは言葉なのかもしれないね。 だから最後は「ねえ、みんなも みんなの/すきになれる 世界を つくってみない?」。 この絵本を読んでいると、いつのまにか「あやいやうやえやお」が友だちみたいに思えてくるから、不思議だ。 さて、きみは、どんな言葉で、どんな世界を作る?(金原瑞人) 読売新聞2004.09.13 【研究書】 『影の国よ、さようなら』(ブライアン・シブリー:著 中尾セツ子:訳 すぐ書房 1985/1991.10) C.S.ルイスと60を過ぎてから結婚したジョイを中心とした伝記で、とても読みやすい。ナルニア読本を読んだことや断片的な知識はあったけれど、ルイスの全体的な伝記は未読だったので、とても興味深かった。離婚歴のあるアメリカ人女性のジョイと、既に神学者、評論家、教授として地位を得ていたルイスの、老年になってからの出会い、その後、ジョイの体を蝕む病魔との闘いの中で、あらゆる障害を乗り越えてはぐくまれたすばらしい愛情に、人生の奇跡を見るよう。 母親が早世して抱えることになった心の傷、兄との生涯のきずな、学校時代、大学時代、無神論者からキリスト者へ改宗したときの心の悟りなど、基本的だけどだからこそおもしろいエピソードの数々である。 アスランは、私は、谷本誠剛先生がおっしゃるように(『児童文学事典』、東京書籍)文学的想像力そのものだと思うのだが、こういう周辺情報を先に読んでしまうと、やはりナルニアはアレゴリー以外の何物にも思えなくなってしまいそう。でも、私は児童文学研究者なので、やはり、ナルニアを描くためにルイスが「ファンタジー」の形式を用いたことや、少年時代に親しんだ北欧神話やギリシア神話の影響を受けた世界像などを考えたい。 それにしても、ジョイとの出会いと結婚、死別の経験ののちに、「影の国からまことの国へ」成仏を得心したルイスはすごい。しかし、死を思い、愛する者の死を受け入れる悲哀の作業は、つまりは普遍的なのだな、とも納得した。 (鈴木宏枝) 『英国レディになる方法』(岩田託子・川端有子 河出書房新社 2004.09) 表紙のスクラップブックの少年少女がなんともヴィクトリア朝期のイギリスである。 児童文学でもなじみの深いヴィクトリア朝時代のイギリス。児童文学とは切っても切れない「女性と子ども」の博物誌が見当たらないことをきっかけに、この一冊が作られた。カラーの写真、絵、図版が多く、華やかかつ実用的かつ学術的である。 著者二人がイギリスで実際に写真を撮り、美術館や博物館に取材し、オースティン、ブロンテ、ディケンズなどヴィクトリア朝時代の英文学、あるいは、キャロル、ピアス、ボストン、オールコットなどの児童文学の場面の引用をちりばめながら解説する。その時代を旅してきた人物のエッセイを読むような分かりやすさとユーモアがある。 chapter1 少女時代 chapter2 結婚式 chapter3 奥様家業 chapter4 子ども時代 chapter5 年中行事 chapter6 弔い 女性の半生を追う章立ての中で、少女時代なら、「サンプラー」や「コルセット」や「舞踏会」、奥様家業なら「ティー・タイム」や「家政の手引書」などの項目がある。以前、ゴッデンの『人形の家』を原典で読んでいたとき、「サンプラー」は刺繍関係の事典で、「ドール・ハウス」は工芸や人形関係の事典でそれぞれ実物の写真を探したことがある。本当は、これらは、同時代に並存していたものである。それを一度に紹介した本は、探してもなかなか見つからなかったので、その意味でも、貴重だろう。 今はアンティークな品々が実際に使われていた時代である。だが、当時の価値観や習俗は、21世紀の現代にも(日本にさえ)受け継がれていて、そのつながりが興味深い。インスタント食品は19世紀後半には既に家庭の主婦や料理人が便利に使っていたそうだ。――そういえば、20世紀初頭、赤毛のアンが「アビリルのあがない」を勝手に投稿されてショックを受けた話でも、ダイアナが応募したのはベーキングパウダーの懸賞小説だったが、これも、海を越えてやってきた当世の流行だったというわけだ。 イギリス文化を追う上でも、子どもと女性の生活史を追う上でも、もちろん、ただ楽しみのためにでも、おもしろい。 髪を編んでつくるアクセサリー(想念がこもっていそう…)や、かわいらしすぎるおまるや、嫁入り支度セットの「トルソー」の中身など、異なる時代の、それでいて今に通じる「もの」がたりである。 (鈴木宏枝) 『10代のメンタルヘルス6・自殺』(ジュディス・ピーコック 上田勢子訳 大月書店 2000/2004.10 1800円) シリーズ第2期刊行開始。ラインナップは、『自殺』『親の離婚』『ストレスのコントロール』『喪失感』『ADDとADHD』。 誤解されそうな表現になってしまうが、ドキドキする。今の10代が抱えているシンドイことを真正面から採り上げたテーマたちだから。 今回の『自殺』は、第一期の3巻目『うつ病』ともリンクした内容。自殺とされる出来事の背景の一つにうつ病が存在しているのを指摘する。悩みから自殺という流れだけではなく、うつ病によるそれの存在を丁寧に解説してくれる。うつ病(に限らず精神性疾患)は、差別的視線の存在のために、隠されたり、かかっていることを親が認めなかったり、受け入れられなかったりしてしまうけれど、病気の一つとして周りも本人も認知し、治療をすれば、「自殺」と見えた出来事が回避される可能性は高まるのだ。(hico) |
|