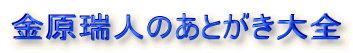
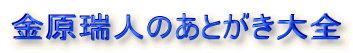
|
1.祝50! なんと、連載50回目である。年齢もちょうど50歳。四捨五入すると100歳である。めでたい。 というわけで、山口百恵のトリビュート・アルバム(MOMOE TRIBUTE)の1と2を聴きながら、これを書いてる(柳ジョージの「夢先案内人」とか、いい味出してるんだよな)。 ちょうど、「ひと夏の経験」がはやっていた頃、浪人仲間四人(池原、今井、谷平、小谷)と一緒に、水戸にいった。池原の家に泊めてもらった……と思う。そして大洗海岸へ。まさに灼熱の太陽のもと、五人で海岸に陣取って、浪人という身分にもかかわらず、ひと夏の経験とばかり、相手をしてくれそうな女の子をさがしていたのだが、なかなか見つからず、ようやく谷平が見つけてきたのが、たしか中学生三人か四人のグループだった……と思う。ほかのメンバーは、おいおい、中学生かよう、とか言いつつも、それなりに楽しくて、夜は海辺でみんなで花火をした……という思い出がある。もちろん、女の子たちとはそれっきりだったのだが、海岸のあちこちのラジカセから流れていたのが「ひと夏の経験」だった。それはとても鮮烈に覚えている。 というわけで、山口百恵はなぜか、青春の歌なのである。しかし最近の好みは、「曼珠沙華」とか「愛染橋」なのだが。 いや、それはさておき、やっぱり、山口百恵の歌はいいなと、ついつい思ってしまう。メロディーもいいけど、歌詞もいい。とくに、宇崎竜童と阿木耀子のコンビはいいなあ。この時代のふたりの歌は、どれもいい。人生、そういう一瞬というのがあると思う。山口百恵も、まさにその一瞬を見事に演出して、最後に「さよならの向こう側」を歌っていなくなってしまった。 そうそう、水戸の大洗海岸でもうひとつ、すごい思い出がある。じつは、朝から晩まで海岸で寝ころんだり泳いだりしていたせいで、全身火ぶくれ状態。東京にもどったときは、歩く赤達磨状態。次の日、病院にいったら、先生にあきれられてしまった。「これくらい焼く人も珍しい……というか、よく平気だったね」。一週間は、もらった薬を塗っていた。 この時期の山口百恵(浪人時代)、ユーミン、中島みゆき、あと大瀧詠一(大学院時代)、そのすぐあとのサザンはかなり印象に残っている。 と、ここまで書いてきて、ふと思ったんだけど、音楽に関しては恥ずかしいほど、むちゃくちゃ普通のルートをたどっているらしい。おそらく、ここでこんなことを書いてるのは、酔っているせいだと思う。 2.あとがき 先先月末から今月にかけて出た本は四冊。 『シャープ・ノース』(カプコン) 『ミッシング』(竹書房) 『小さな白い車』(中央公論新社) 『かいじゅう ぼく』(主婦の友社) 『四月の痛み』(原書房) 最後の『かいじゅう ぼく』は絵本なので、あとがき、なし。 というわけで、今回は三つ。 3.あとがき(『シャープ・ノース』『ミッシング』『小さな白い車』『四月の痛み』) あとがき(『シャープ・ノース』) あっちをむいてもクローン、こっちをむいてもクローン、とにかく本屋に行けば、クローンがらみの小説があふれている。欧米でも日本でもそれはまったく変わらない。アメリカでは「レプリカ」というクローン物のシリーズが出ているし(未訳)、最近では、二00二年に出版されて全米図書賞を受賞したヤングアダルトむけの『砂漠の王国とクローンの少年』(ナンシー・ファーマー)が抜群におもしろかった。いや、小説に限らない。二00一年にはフィリップ・K・ディック原作の短編が『クローン』という映画になっている(ただし、ここに登場するのは厳密に言うとクローンではない)。 もちろん、日本でもその手のものはたくさんある。清水玲子の『輝夜姫』は権力者や有力者のドナーとして作られるクローンを扱った傑作SFマンガで、コミック版はすでに二十四巻を越えてますますおもしろくなってきた。芝居のほうでも同じような流れはあって、新国立の小劇場で上演された篠原久美子の『ヒトノカケラ』もやはりクローンを扱った芝居。キムラ緑子の熱演もあって、見応えのある舞台になっていた。 二十世紀、SFに限らず、小説や映画などにあたりまえのようにロボットが登場してきたのと同じで、二十世紀の終わりから二十一世紀にかけて、クローンが続々と登場してくる。そしてクローンが出てくれば、その中心、あるいは脇にすえられるテーマはほぼ同じ。クローンは個性ある人間なのか、コピーにすぎないのか、また、クローン人間はアイデンティティをどこに求めればいいのか、といった問題だ。これもまた二十世紀のロボット物でよく扱われた問題だった。しかし一八一八年に発表されたメアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』に、すでにその原型はある。 考えてみれば、材料は違うものの、パターンはほぼ変わりなく、同じテーマが時代時代の衣装をまとって、繰り返し問われて続けているということだろう。 だからこそ、その手の新しい作品には必ず、「+α」が求められる。つまり、クローン物があふれている現在、それでもクローン物を書く作家は、それなりの創意と準備と決意がなくてはならない。だからこそ、読み手は、そこを期待する。 そしてこの『シャープノース』は見事、その期待に応えてくれる。 『シャープノース』のなによりの特徴は、その疾走感だろう。ハイテンポのストーリー展開と、全編を貫く疾走感、これがなんとも爽快だ。下手なロードムーヴィーなど足許にもよらない緊迫感にあふれている。 目の前で殺人を目撃し、危険を感じた少女ミラは逃げる。雪のなかをひたすら逃げる。そして自分を危険におとしいれている謎を追う。激しい吹雪のなかを、海に伸びる橋の上を、海上を、海中を、街のなかを、高架橋を、逃げながら、追っていき、追いつめられながら、追いつめていく。読んでいくうちに、ぞくぞくするような快感がわいてくる。おそらく昔なら「スリルとサスペンス」という言葉で賞賛されただろう。 それから、舞台になっている未来世界のイメージがいい。世界規模の気温変化によって極地の氷がとけ始め、低い土地だけでなく、いくつもの都市が水面下に姿を消していくという設定は、珍しくもなんともない。しかし水面ぎりぎりのところに広がる貧民街、そこで起こる事件、尻尾をくわえた蛇を信奉する宗教、そこで暮らす人々、延々と続く高架橋を我が物顔でのし歩く鉄の怪物、などのかもしだす暗く不気味な雰囲気は、天才少女ミラの鮮やかな疾走を効果的に浮かびあがらせている。 とにかく、追跡劇、逃走劇、謎解きの三本の紐が巧みに編まれていて、読者は翻弄されながら、一気に、しかし疲れ切って、最後までたどりつくだろう。が、その瞬間、この物語は、すさまじい勢いで方向を変え、新たな地平目指して飛びだそうと身構える。 そう、この上巻の終わりの部分は、下巻にむけての猛ダッシュなのだ。その下巻を訳者は、いち早く読むことができる。たぶん、原稿の段階で読めるはず。久々に訳者であることの幸せをかみしめているところだ。 作者、パトリック・ケイヴは、イングランド南西部のバースの生まれで、現在三十代とのこと。『シャープノース』は、Number 99、Last Chance、につぐ作品とのこと。 最後になりましたが、編集の八尾剛己さん、原文とのつきあわせをしてくださった石田文子さんに、心からの感謝を! 二00五年三月十八日 金原瑞人 訳者あとがき(『ミッシング』) 『青空のむこう』『13ヵ月と13週と13日と満月の夜』『チョコレート・アンダーグラウンド』『海のはてまで連れてって』と、ほぼ毎年のようにアレックス・シアラーの小説を訳してきて思うのだが、この人はすごい。 書くたびに、題材もテーマもがらりと変わる。交通事故で死んだけれどこの世に残ってしまった少年の物語、老婆になってしまった少女の物語、チョコレートが禁止された世界で戦う少年たちの物語、海賊と戦う双子の少年の物語……といった題材のなかに、やさしさ、勇気、抵抗、父と子のつながりといったテーマがしっかり描かれていく。これに『魔法があるなら』と『スノードーム』を加えると、シアラーの世界はますます広がっていく。 しかしシアラーがほんとうにすごいのは、それぞれの作品がそれほどまでに様々な世界を描きながらも、それぞれが驚くほどよくできていて、それぞれに魅力的だということだ。 というわけで、この最新作の『ザ・ロスト』(The Lost)、また新しい題材、新しい手法、新しいテーマである。 主人公はジョー。まず、親友のジョナといっしょに消防車を追いかけるのが話の発端。ジョナはいつも、手に入らないもの、不可能なことに心を奪われて、必死にそれを追いかけるようなところがある。消防車を追いかけたところで、追いつくはずはない。ジョーはそのうちあきらめるが、ジョナはあきらめない。「おい、こなくてもいいけど、おれのことおはだれにも言うなよ。約束だぞ」とジョーにいって、消防車のあとを追っていく。そしてそのまま消えてしまった。 ここから物語が始まる。最初は、いつものことだとのんびりかまえていたジョーも、ジョナが夜になってももどってこなかったことを知って不安になる。が、ジョナとの約束があるから、人には話せない。やがて警察が動き始める…… ここからのジョーの心の動き、葛藤、苦しみ、これがこの本の前半のテーマで、後半はジョーの信念と戦い……延々と続く、まわりの世界との戦い、そして自分との戦い……それが中心となっていく。刻々とゆらぎ、変わっていくジョーの気持ちと、それでも変わらないジョーの固い信念のせめぎ合い、シアラーはこれを残酷なほどに、たくみに描いていく。たとえば…… ジョナを見つけるためには、自分も同じ場所へいかなければならない。それがどこなのか、そのうちわかるときがくる。何か耳にしたり、目にしたりすれば、それがジョナを見つける日だ。数時間先か、数年先かはわからない。だけど「そのとき」がきたらわかる。通りでサイレンが鳴ったときか、空に星が流れたときか。「それ」が何かはわからないが、ジョナが追い求めたようにして、自分も「それ」を追いかける。そして、消えるのだ。ジョナが消えたように。そうすれば、ジョナに会える。 この部分を読んだときの感動は忘れられない。いきなり消えてしまった親友をひたすらさがし、ひたすら追い続けるジョーの気持ちがここに凝縮されている。「そして、消えるのだ。ジョナが消えたように。そうすれば、ジョナに会える」という言葉、この言葉のあとはこう続く。「だが、そうするにはすべてを失う覚悟をしなければならない」 はたして、ジョーはジョナに会えるのだろうか。いや、そもそもジョナは生きているのだろうか。そのへんは、ここに書くわけにはいかない。しかし、ひとつだけいえるのは、シアラーは、読者を絶望の淵に投げこんで、物語を終わらせることはない、ということだ。 ジョーがジョナに会えるにしろ、会えないにしろ、ジョナが生きているにしろ、死んでいるにしろ、最後には十分に納得のいくハッピーエンドが待っている。 『バッテリー』を書いたあさのあつこが、こんなことを書いている。 これは一般書でもそうかもしれませんが、私は児童書においてただ一つタブーがあるとしたら、それは性的表現とか、殺人などといったことではなく、絶望だろうなと思うのです。人生ってこんなものだとか、死んで終わりだとか、破滅して終わりだとか、それだけは語りたくない。ありきたりな希望ではなくて、ほんとうにささやかであっても、やはり若い方たちがこれから生きて行く価値のある未来があるんじゃないかみたいなことを語りたい。(「読書のいずみ」〈全国大学生活協同組合連合会〉) だから、安心して最後まで突っ走ってほしい。そう、ジョナのように。 この小説の舞台になっている町について、少しだけ説明を。名前はグラストンベリ。イギリス南西部のサマセット州にある小さな町で、人口七千人。ところがここにはアーサー王の墓がある。十二世紀、王妃グウィネヴィアの墓とともに、修道院の敷地内で見つかったということになっている。またこの本にも出てくる「グラストンベリ・トール」は円錐形の山で、ケルトの古代宗教、ドルイド教においては霊的なパワーの源であると考えられていた。そんなこともあり、町にはニューエイジやヒーリング関係の店が立ち並び、なんとなく“あやしげ”な雰囲気がある、らしい。 最後になりましたが、編集の中山智映子さん、翻訳協力者の小川美紀さん、原文とのつきあわせをしてくださった鈴木由美さん、細かい質問にていねいに答えてくださったアレックス・シアラーさんに心からの感謝を! 二00五年七月四日 金原瑞人 訳者あとがき(『小さな白い車』) 『ティモレオン センチメンタル・ジャーニー』『コンスエラ 7つの愛の狂気』と、強烈な作品で英語圏の読書界を引っかき回してきたダン・ローズ。彼の作品はどれも、グロテスクで残酷でコミカルで、切なく、ぞっとするほど美しい。よくぞ、これほど魅力的な奇形児@フリーク@が現れたものだと、つくづく感心し、感動したものだ。 そのダン・ローズの新作がこれ。 最初、この原書を見たときには、「おいおい、なんだよ、これ?」という感じだった。なにしろタイトルが『小さな白い車』(The Little White Car)なのだ。表紙も、青地に白抜きの白い車。そのまわりを、赤、薄い青、白の文字が囲っている。そのうえ、名前まで変わっている。ダン・ローズ(Dan Rhodes)ではなく、ダヌータ・デ・ローズ(Danuta de Rhodes)になっているのだ。 「え、女?」 気になって著者紹介を読んでみたら、一九八0年生まれ。パリとリオデジャネイロで育ち、十二歳のときから、ファッション雑誌に記事を書き始め、十四歳のときに、"Le Cochon d'Inde"(『インドの豚』?) という映画の脚本を書き、これが注目され、次作を書くことを勧められたが、学業に専念……といった内容。 もちろん、嘘、というかフィクション。 本人は一九七二年、イギリス生まれ。もちろん、男。 しかしこれを読んだとき、よくやってくれるなあという、ある種感動に近いものがあった。いかにもダン・ローズらしい、しゃれっ気たっぷりの演出といったところだろうか。 こういった演出が、じつはそのまま、この本の雰囲気と重なっている。舞台は一九九七年のパリ。主人公はヴェロニクという女の子。ヴェロニクがそれまでつきあっていた、口ばかり達者で実行力もなく、やる気もない、どーしよーもない現代音楽おたくのジャン=ピエールと別れようと心に決め、愛犬セザールを連れて車に乗りこむ。ところがワインとマリファナのせいで、頭のなかはぐるぐる状態。次の日、ガレージに入って車をみると、接触事故の跡が。そしてテレビをつけたら、チャールズ皇太子らしき男の人が病院の外に立っている映像とダイアナ妃の写真。ニュースを聞いたヴェロニクは耳を疑う。 「マジ?」ヴェロニクはつぶやいた。「あたし、プリンセスを殺しちゃった」 こうして、物語は幕を開ける。『ティモレオン』や『コンスエラ』とは打って変わって、あくまでも軽いタッチ、軽いノリで、ユーモラスに進行。ただ、全体に流れるユーモアは、軽く流れるかと思うと、たまに少し濃いめだったりするし、登場人物はひと癖もふた癖もあるやつばかり。ヴェロニクの証拠隠滅に協力する親友のエステル(頭のネジが数本飛んでいる)、定期的にジャン=ピエールの部屋に勝手に入りこんでは、そこにだれがいようとまったく知らん顔で、黙々とサンドイッチを食べ、伝書鳩を窓から放つチェリーおじさん(鮮烈なエピソードを残す)、などなど。 しかし、まずなにより魅力的なのは主人公ヴェロニカだろう。 単純で、浅はかで、優しくて、したたかで、手強くて、とてもキュート。唐突に「ロンドンに行って足の指を切ってもらってくる」とエステルに言ったりするところもまた、変にかわいい。 ここまで書いてきてふと思った。『デリカテッセン』『ロスト・チルドレン』という強烈な作品で世界をあっといわせたフランスの映画監督、ジャン=ピエール・ジュネが、あるとき、ふっと魔が差したように作った、甘く、ちょっと切なく、とてもキュートな映画『アメリ』、これこそまさにこの『小さな白い車』かもしれない。 ただ、『アメリ』はクレーム・ブリュレだったが、『小さな白い車』はかなり味わいが違う……フルーツチーズや、ナッツのチーズもあるけど、隅のほうにブルーチーズやウォッシュタイプの強烈なチーズもある、そういうチーズの盛り合わせの皿のような気がする。 最後になりましたが、編集の香西章子さん、つきあわせをしてくださった鈴木由美さん、細かい質問にていねいに答えて下さったダヌータ・デ・ローズさんに心からの感謝を! 二00五年七月七日 金原瑞人 訳者あとがき(『四月の痛み』) わたしはかつて、三十歳までに死ぬと誓っていた。二十八歳になると、四十歳に延期した。その次はたしか七十歳だった。明日、わたしは八十六歳になる この老人が老人ホームでつづった日記がこの本。四月二日に始まって、次の年の四月六日に終わる。 ここにはホームでのいろいろな出来事、仲間とのふれあい、過去の回想、日々近づいてくる死に関する考察、日々生きていくことへの思い……などが語られている。 仲間といえば、ユーモアのセンス抜群で、いつも脱走やいたずらを考えては、たまに実行に移すウェーバー。主人公は「不朽の名声が欲しいし、死んでからも人々にわたしのことを考えてもらいたいと」と思っていたが、ウェーバーは「自分以外に人間になりたがることなどけっしてない」 そんなウェーバーを見て、主人公はふと考える。 そもそも、他人より優れた者とか劣った者などいないのではないか? おそらく、ウェーバーはそれが真実だと信じているのだろう。だからこそ、死を恐れないのだ。わたしは生まれてこのかた、毎日、死を恐れている。死にともなう痛みだけでなく、哲学的な意味でも死が怖い。死という概念と、それにまつわるこまごまとしたことすべてが怖い。 全編に流れる、こういった主人公の思索と感慨はとてもユニークで、われわれとは少しずれた視点から世界をながめているようであると同時に、鋭くおもしろいところをついてくる。 目には匂いをかいだり、音を聞いたり、味わったり、触れたりするためにもある。想像したり、悩んだり、実在しない世界から実在する星を見つけるためにもある……わたしの目は目に見えるものすべてであり、見えないものすべてである。両目が開いているとき、わたしの目には無限大の二倍の能力がある。閉じれば、能力はさらにあがる。 これを読んだときすぐに、後藤繁雄の『五感の友』(リトルモア)を思い出した。この本にこんな文章がある。 すべての見えるものは、見えないものに触っている。聞こえるものは、聞こえないものに触っている。感じられるものは、感じられないものに触っている。おそらく……これは志村さんがご自身の本の中で引用されていたノヴァーリスの言葉である。僕は、この言葉に出会った時、すぐさま日記ノートに書き写した。自分がずっと言いたかったもどかしさが、見事に簡潔に記されていたからだ。 文中、「志村さん」とあるのは、染織作家の「志村ふくみ」のこと。「ノヴァーリス」というのはドイツ初期ロマン派の詩人・作家。 そう、『四月の痛み』を読んでいると、「ずっと言いたかったもどかしさが、見事に簡潔に記されて」いる文章によくぶつかる。 それだけでも十分に、いや十二分におもしろい。たとえば、次のような部分もそうだ。 わたしが妻と結婚したのは、ほかに選択の余地がなかったからにすぎない。彼女を自分のものにせずにはいられなかった。それだけのことだ。この考えは、いささかも変えるつもりはない。変えてどうなる? 長い目で見れば、正しい選択とか間違った選択などというものはない。あるのは選択をしたかしなかったか、その違いだけだ。 そう、そうなんだ、と思わずいってしまいそうになる言葉や考察に、この本はあふれている。どこを読んでも、はっとさせられ、次の瞬間には納得させられる。 しかしこの本はエッセイ集ではない。そういったことを考えている、いや、考えざるをえない老人が主人公の小説だ。だから、その老人のいらだちや恐怖も語られる。いうまでもなく、「死」を目前にした人間の思いだ。それがまた、驚くほどリアルに描かれていく。しかしいうまでもなく、死んだことのない人間は死を知りようもなく、そこで語られるのは死ではなく生なのだ。そのパラドックスは、生きている限りどこまでも追いかけてくる。この本は死を目前にした老人が語る「生」についての本だといっていい。 この作品の最後の部分にいたったとき、読者はそれを、ある種の甘い切なさとともにかみしめるに違いない。 それにしても、この八十六歳の老人の話は、フランク・ターナー・ホロンが二十六歳のときに書いた最初の小説。装いはずいぶん古い感じがするものの、よく読むと、若い。自分にはとても想像もできない老齢を想像し、「老い」というものをしっかり手元に引き据えて書いたこの小説、信じられないほどリアルだ。生も死も、人生も死も、老いも死も、若さも死も、すべてがこの薄い一冊に凝縮されている。 読み飛ばしたくなる小説が量産される今日、ゆっくりじっくり読みたくなる一冊だと思う。 最後になりましたが、原文とのつきあわせをしてくださった鈴木由美さん、この作品をぽんと投げてくださった編集の中村剛さんに心からの感謝を! 二〇〇五年八月二十二日 金原瑞人 4.お知らせ 八重洲ブックセンターの上に八重洲座というホールが誕生。100席ちょっとの小さな空間だけど、ちょっとおしゃれで、9月から、毎月下旬に古典芸能を中心にした公演を行うことになり、最初、その企画にたずさわることになりました。今のところ、こんな感じです。 9月27日(火)6:30から。 女流義太夫。金原のHPでチラシのPDF見られます。 10月26日(水)6:30から。歌舞伎解説者のおくださんと義太夫のジョイント。ポプラ社の歌舞伎絵本『義経千本桜』(橋本治+岡田嘉夫)がらみ。11月23日(水)午後。歌舞伎解説者のおくださんと義太夫のジョイント。ポプラ社の歌舞伎絵本『仮名手本忠臣蔵』がらみ。 1470円という、映画の前売りよりも安い値段で、90分、古典芸能を楽しんでいただこうという企画。ぜひお立ち寄りください。 「野生時代」(角川書店)の11月号から三ヶ月、海外の短編小説がひとつずつ掲載されることになった。最初はエリザベス・マクラッケンの「死んだりしたら、それこそ……」(舩渡佳子訳)、次がT・コラゲッサン・ボイルの「掘る男」(圷香織訳)、最後がピンクニー・ベネディクトの「ミラクル・ボーイ」(西田登訳)。そうそう、いうまでもなく、『バースデー・ボックス』を出すことになった勉強会の面々が訳している。どれも素晴らしい短編なので、ぜひ! 「小説すばる」に「ぼくの訳したい本」というエッセイ(仮タイトル)を11月号から掲載の予定。 |
|