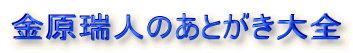
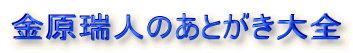
|
1.ジュリアン 「ジュリアン」といっても人の名前ではない。出版社の名前だ。 以前、この「あとがき大全」で書いたのだが、二年ほど前、青山出版社からドナ・ジョー・ナポリの作品がシリーズで出ることになった。Beast、Crazy Jack、Zel、Breathの四冊だ。それぞれ、『美女と野獣』、『ジャックと豆の木』、『ラプンツェル』、『ハーメルンの笛吹き』のパロディ。ところが、青山出版社が出版方針を変更し、すべて出版が中止になった。Beast などは、すでに訳し終わって校正の段階だったのだが、これも中止。そこで、この場を借りて、「どこか代わって出版してくれませんか!」と呼びかけたところ、ありがたいことに、編集者の倉澤さん、牧野出版の佐久間さんが協力してくださって、ジュリアンの出版局から四冊すべて(じつは、青山出版社から出ることになっていて中止になったものが、あと二冊あったのだが、これもふくめて、六冊すべて)、出してもらえることになった。心からほっとした。もう感謝、感謝、である。 なにしろ金原が選書して、翻訳を頼んだり、共訳を頼んだりしていたので、心苦しくて。 そしてまずそのうちの二冊がジュリアンからめでたく出版の運びとなった。『野獣の薔薇園』と『クレイジー・ジャック』。 『逃れの森の魔女』でナポリを知ってからというもの、彼女の作品は出るたびに読んでいるのだが、読むたびに驚かされる。元になっている作品を信じられないほどユニークに語り直す、あの想像力。また、ナポリの場合、各作品を必ず、ある時代のある場所を舞台に決めて書くのだが(たとえば、『逃れの森の魔女』の場合は中世のドイツらしい場所)、その舞台について徹底的に調べて、とてもリアルに描写していく、その緻密さ。こういった特徴は『野獣の薔薇園』や『クレイジー・ジャック』にもそのままあてはまる。 ともあれ、『逃れの森の魔女』の好きな方はぜひ読んでみてほしい。『野獣』は久慈さんの訳。『ジャック』は金原と小林さんの共訳。 2.『四月の痛み』『トロール・ミル』『クレイジー・ジャック』 今月は、この三冊のあとがきを。 『四月の痛み』は一般書。 訳者あとがき(『四月の痛み』) わたしはかつて、三十歳までに死ぬと誓っていた。二十八歳になると、四十歳に延期した。その次はたしか七十歳だった。明日、わたしは八十六歳になる この老人が老人ホームでつづった日記がこの本。四月二日に始まって、次の年の四月六日に終わる。 ここにはホームでのいろいろな出来事、仲間とのふれあい、過去の回想、日々近づいてくる死に関する考察、日々生きていくことへの思い……などが語られている。 仲間といえば、ユーモアのセンス抜群で、いつも脱走やいたずらを考えては、たまに実行に移すウェーバー。主人公は「不朽の名声が欲しいし、死んでからも人々にわたしのことを考えてもらいたいと」と思っていたが、ウェーバーは「自分以外に人間になりたがることなどけっしてない」 そんなウェーバーを見て、主人公はふと考える。 そもそも、他人より優れた者とか劣った者などいないのではないか? おそらく、ウェーバーはそれが真実だと信じているのだろう。だからこそ、死を恐れないのだ。わたしは生まれてこのかた、毎日、死を恐れている。死にともなう痛みだけでなく、哲学的な意味でも死が怖い。死という概念と、それにまつわるこまごまとしたことすべてが怖い。 全編に流れる、こういった主人公の思索と感慨はとてもユニークで、われわれとは少しずれた視点から世界をながめているようであると同時に、鋭くおもしろいところをついてくる。 目には匂いをかいだり、音を聞いたり、味わったり、触れたりするためにもある。想像したり、悩んだり、実在しない世界から実在する星を見つけるためにもある……わたしの目は目に見えるものすべてであり、見えないものすべてである。両目が開いているとき、わたしの目には無限大の二倍の能力がある。閉じれば、能力はさらにあがる。 これを読んだときすぐに、後藤繁雄の『五感の友』(リトルモア)を思い出した。この本にこんな文章がある。 すべての見えるものは、見えないものに触っている。聞こえるものは、聞こえないものに触っている。感じられるものは、感じられないものに触っている。おそらく……これは志村さんがご自身の本の中で引用されていたノヴァーリスの言葉である。僕は、この言葉に出会った時、すぐさま日記ノートに書き写した。自分がずっと言いたかったもどかしさが、見事に簡潔に記されていたからだ。 文中、「志村さん」とあるのは、もう亡くなった染織家の「志村ふくみ」のこと。「ノヴァーリス」というのはドイツ初期ロマン派の詩人・作家。 そう、『四月の痛み』を読んでいると、「ずっと言いたかったもどかしさが、見事に簡潔に記されて」いる文章によくぶつかる。 それだけでも十分に、いや十二分におもしろい。たとえば、次のような部分もそうだ。 わたしが妻と結婚したのは、ほかに選択の余地がなかったからにすぎない。彼女を自分のものにせずにはいられなかった。それだけのことだ。この考えは、いささかも変えるつもりはない。変えてどうなる? 長い目で見れば、正しい選択とか間違った選択などというものはない。あるのは選択をしたかしなかったか、その違いだけだ。 そう、そうなんだ、と思わずいってしまいそうになる言葉や考察に、この本はあふれている。どこを読んでも、はっとさせられ、次の瞬間には納得させられる。 しかしこの本はエッセイ集ではない。そういったことを考えている、いや、考えざるをえない老人が主人公の小説だ。だから、その老人のいらだちや恐怖も語られる。いうまでもなく、「死」を目前にした人間の思いだ。それがまた、驚くほどリアルに描かれていく。しかしいうまでもなく、死んだことのない人間は死を知りようもなく、そこで語られるのは死ではなく生なのだ。そのパラドックスは、生きている限りどこまでも追いかけてくる。この本は死を目前にした老人が語る「生」についての本だといっていい。 この作品の最後の部分にいたったとき、読者はそれを、ある種の甘い切なさとともにかみしめるに違いない。 それにしても、この八十六歳の老人の話は、フランク・ターナー・ホロンが二十六歳のときに書いた最初の小説。装いはずいぶん古い感じがするものの、よく読むと、若い。自分にはとても想像もできない老齢を想像し、「老い」というものをしっかり手元に引き据えて書いたこの小説、信じられないほどリアルだ。生も死も、人生も死も、老いも死も、若さも死も、すべてがこの薄い一冊に凝縮されている。 読み飛ばしたくなる小説が量産される今日、ゆっくりじっくり読みたくなる一冊だと思う。 最後になりましたが、原文とのつきあわせをしてくださった鈴木由美さん、この作品をぽんと投げてくださった編集の中村剛さんに心からの感謝を! 二〇〇五年八月二十二日 金原瑞人 訳者あとがき(『トロール・ミル』) すさまじい風と降りしきる冷たい雨の中、ひとりの女が駆けてきて、ペールの手に赤ん坊を押しつけ、去っていった。若い漁師、ビヨルンの美しい妻チェルスティンだ。チェルスティンはそのままふり返りもしないで海岸へ走っていくと、灰色の波に飛びこんだ。 ペールは赤ん坊を抱いたまま、大急ぎでビヨルンに知らせにいく。 ビヨルンは舟に勢いよく飛び乗った。ガラガラ転がるオールをひっつかむと、猛烈な勢いで水をかきだし、体を右に左にくねらせて、海の上にチェルスティンの姿を必死に捜した。ビヨルンのひび割れた叫び声がペールの耳に届いてくる。 「チェルスティン! チェルスティン、もどってこい……」 舟は白く砕ける波頭を飛びこえ、雨と闇のなかに飲みこまれていった。 ペールは目をみはった。まるで小さなしみのように、つやつやした頭が海面で浮いたり沈んだりしているのだ。夢中で走り出したが、それはすぐ消えてしまった。ところがそこへ、また別の頭が。と思う間もなく、さらにまた別の頭が――それからはもう、次から次へと現れて、波のうねりにあわせてぽかぽか浮かんだり沈んだりしている。波のまにまに黒っぽい体がさっと現れては、また消えた。 「アザラシだ!」 ペールの声がかすれた。 『トロールフェル』でもそうだったが、キャサリン・ラングリッシュという作家は物語を作るのがうまい。とくにはじまりかたが素晴らしい。 『トロールフェル』の続編『トロールミル』でも、そのうまさは舌を巻くほどだ。 トロールの地底王国からもどってきて三年、ペールは十五歳になる。あくどい叔父たちもいなくなり、ペールは親友のヒルデの家族の一員として幸せな毎日を送っていた。そこへ、いきなりこの事件。ペールはしかたなく、世話になっているヒルデの家にもどる。そして耳にしたのが、アザラシ女のうわさだった。チェルスティンは、ビヨルンが漁にでかけたときみつけて無理やり妻にしたアザラシだというのだ。 チェルスティンは海に消えたままもどってこない。ビヨルンはうわさについてはなにもいわないが、不安で居ても立ってもいられないのは、だれの目にもわかる。そして、ペールがあずかった赤ん坊は不思議と静かで、いつもおとなしい。あのうわさは本当なのか。 いっぽう、ヒツジが次々に盗まれ、しばらくおとなしかったトロールたちがあちこちで不穏な動きをみせだした。いったい、なにが起こっているのか。 また、ペールの叔父たちがいなくなってから、使われていなかったはずの水車小屋の水車が夜になると回り始める。いったい、だれがなんのために動かしているのか。 そういった不気味な事件と謎がからみあって、物語が大きく動いていく。これにペールの、かわいい少女ヒルデに寄せる気持ち加わる。 今回も前と同じようにトロール、ニース、グラニー・グリーンティース、ラバーなどが登場して、物語はユーモラスにもりあがったかと思うと、ぞっとするような場面になったりする。 北欧の香りたっぷりの冒険ファンタジーの第二弾。どうぞ、ゆっくり楽しんでください。 二00五年九月 金原瑞人 訳者あとがき(『クレイジー・ジャック』) 妙に相性のいい作家というのがたまにいる。もちろん、どんな作家であれ、書いた作品がすべておもしろいということはないし、まれには駄作もないとは限らない。しかし作品の出来は善し悪しがあるとしても、なぜかどれもがしっくりくる、読んでいて心地よい、そしてエンディングも深くうなずけるうえに深く迫ってくる、そんな作家が何人かいる。日本の女性作家でいえば、江國香織、川上弘美、森絵都、三浦しをんあたりがそうだ。英語圏の女性作家でいえば、フランチェスカ・リア・ブロック、ジェラルディン・マコーリアン、ドナ・ジョー・ナポリあたりがそうだ。新しい作品が出ると、つい読んでしまう。ここに異色の新しい作家をひとり付け加えれるとすれば、オーストラリアのシンシア・ハートネットだろうか。 さて、そのうちのひとり、ドナ・ジョー・ナポリだが、とにかく出会いが強烈だった。作品は『逃れの森の魔女』(青山出版社)。原書は表紙も装丁も、はっきりいって、むちゃくちゃださい本だった(日本語版を送ったところ、作者から「とても美しい本で、思わず泣いてしまいました」というメールがきた。表紙は出久根育さん) なぜそんなものを読み出したかというと、まず薄くて、ちょうど電車の帰りに読み終えることができそうだったのと、冒頭の情景が息をのむほどあざやかに浮かんできたためだった。そして電車の中で読んでいくうち、いつの間にか、主人公の気持ちに自分の気持ちがとけ合っていった。 ナポリの心理描写は、舌を巻くほど巧みで、的確で、きびしく、やさしい。とくに印象に残っているのは、主人公が魔法陣のそばに転がってきた金の指輪を見つけるところだ。容姿が醜いために、いっそう美しい物や宝石にあこがれる主人公は、「天上の美」に輝いている金の指輪を心からほしいと思うが、ふと考える。いや、これは自分のものではない、これは美しい娘アーザのものだ。この指輪はアーザの身を飾り、そのお返しにアーザの輝きがわたしの世界を明るく照らし出す。それでいいのだ。 そう思って手をのばした瞬間……というこの展開は、何度読み返しても切なく恐ろしい。こういったとてもリアルで、読者の胸を突くような心理描写(主人公のコンプレックス、娘への愛情、美しい物への渇望、それを正当化するための方便などなど)が、ナポリの作品の大きな魅力だと思う。 その魅力はこの『クレイジー・ジャック』にも十分にうかがえる。これは「ジャックと豆の木」をヒントに作り上げられた小説、いってみればパロディだが、一種の心理小説であり、また、主人公ジャックの成長小説でもある。そしてなにより、見事な発想の切り返しによって作り上げられた冒険小説でもある。 大道具は、七色の豆、豆の木、巨人、金の卵を産む鶏、金の入ったつぼ、歌う竪琴といった、昔話でおなじみのものだ。が、ナポリの魔法にかかると、それらが昔話という衣を脱ぎ捨て、その本質をむきだしにする。こうして魔法の物語がリアルに、生き生きと、しかし昔話のおもしろさはそのままに展開していく。だから、巨人は巨人であって巨人ではないし、金の卵を産む鶏は、金の卵を産む鶏であって、金の卵を産む鶏ではない。また、この作品のなかでは、ジャックの父親とかわいいフローラという女の子が大きな役割を負っている。いや、それだけではなく、巨人といっしょに暮らしている女もまた、大きな意味をもって登場してくる。 ナポリは昔話やおとぎ話の魔法をはぎとって、その奥に隠された現実を引き出し、それをまた巧みに紡ぎ上げて、現代の昔話を作り上げる。まさに現代の語り部といっていい。 どうか、存分に楽しんでいただきたい。 なお最後になりましたが、編集の津田留美子さん、原文とのつきあわせをしてくださった高林由香子さんに心からの感謝を! 二〇〇五年七月二十四日 金原瑞人 3.おわび 『メジャーリーグ、メキシコへ行く』のあとがきで、「原文とのつきあわせをしてくださった中村浩美さんと野沢佳織さん……」と書いたのだが、野沢さんからメールがきて、「あの、わたし、つきあわせ、してないんですけど」とのこと。ううん、まいった。もうひとかた、だれだっけ? この作品、翻訳があがって出版社に放りこんでからずいぶん時間がたっているから、記憶がどうも……。「わたしです!」というかた、ぜひご連絡を。 4.八重洲座公演 11月は女流義太夫で『仮名手本忠臣蔵』を。これに橋本治+岡田嘉夫の対談がつく。八重洲座初の満員札止め。120席すべて埋まった。 ごひいきのみなさまに、心からの感謝を! ただ、心配なのは12月の八重洲座の公演。こちらは上方若手ナンバーワンの落語家、桂文我さんをお呼びしての企画。金原とのトークと、文我さんが掘り出してきた、いまではだれもやらない落語との組み合わせ。絶対におもしろい! なのに、なぜ心配かというと、公演日が24日、なんと、クリスマスイブの1時と4時の二回なのだ。彼女や彼氏を放っておいて、いや、いっしょに連れて、いやいや、家族総出で、ぜひ、八重洲座へお越しください。 5.エッセイ集 なんと、この「あとがき大全」からの抜粋を中心に編集した、金原初のエッセイ集が12月上旬に出版の予定。タイトルは『翻訳家じゃなくてカレー屋になるはずだった』(牧野出版)。 この場を提供してくださったひこさん、また、飽きもせずおつきあいくださった読者のみなさまに、心からの感謝を! |
|