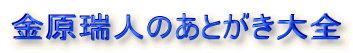
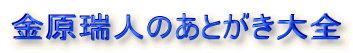
|
あとがき大全(56回目) 1.YAというジャンル これについて、四月号の「小説すばる」の座談会から。 金原 エンタテイメントで売れ線だったミステリーがかつてほどドル箱ではなくなった。以前は、ホラーだけど謎解きの要素があるからミステリーに入れたり、幻想小説なんだけどちょっと無理してミステリーに入れたり、と吸引運動が大きくなってミステリーがどんどん膨れ上がった。それが崩壊した後に、エンターテイメントで何がおもしろいかというのでYAがきている。YAはジャンルじゃなくて、年齢的な区切り方で、そういった意味ではミステリー以上にいろんなものが取り込みやすい。SFであってもいいし、ミステリーでもいいし。 菅原 何でもあり。 金原 主人公が必ずしもYAでなくても、おじいちゃんが主人公でもYA、強引な引き込み方だけど、柔軟性があるから。だから、最近は「おもしろい小説はすべてYAである!」と言い切ることにしているんだけど(笑) ちょっと解説を。この座談会、菅原さんは、銀座の教文館という書店の児童書コーナー「ナルニア国」で働いている店員さん。とはいえ、最初はたまプラーザの子供の本のお店で働いていて、そのうち大学の付属中学校の図書館司書を経て、現在にいたる……という感じ。本を読む学生や、本を買う人たちをしっかり見ている、現場の人。 次に代田さん。メグ・キャボットの『プリンセス・ダイアリー』や、シンシア・カドハタの『きらきら』などで、独自の方向をひたすら進んでいるYA翻訳家。 もうひとりは、オールマイティで、かつての金原に近いスタンスで翻訳活動をしている三辺さん。三辺さん、産経新聞なんかで書評も担当しているところまで、金原に似ている。 この四人による座談会、めいめいが勝手なことをいっていて、あまりまとまりがないのだが、全体を通じて、なかなか楽しい読み物になっているので、もし興味のあるかたは、ぜひ、立ち読みでも。 さて、それはさておき、YAの非常にフレキシブルな特長について、この座談会で強調したのだが、『ぎぶそん』で今回の坪田穣治文学賞を受賞した伊藤たかみが、選考委員の西本鶏介との対談で次のように語っている。 「ヤングアダルトの分野は、エンタテイメントや純文学などほかのジャンルの技術を持ち込むことでさまざまな可能性が広がると感じている」 さらに、集英社の広告雑誌「青春と読書」の次号で(おそらく、まだ出てない)、コバルト文庫30周年を記念しての対談で、唯川恵と大岡玲が対談をしていて、そのなかで、こんなところがある。 「というのもコバルトは、主人公が若いという以外に縛りはなくて、ファンタジーもあるし推理ものもあるし社会はみたいなのもあるし、もちろん少女小説の伝統を踏まえたものまで全部入っている」 話しているのは大岡さん。 かつて(十数年前)、ヤングアダルトというジャンルは売れなかったし、出版社も出そうとしなかった。ぼくが福武書店でロバート・ウェストールの『かかし』や『ブラッカムの爆撃機』を出したときも、編集サイドは「ヤングアダルト」という言葉を使おうとしなかった。ずいぶん、時代の差を感じてしまう。 時代というのは、こういうものなのかな、という気もする。ある意味、ばかばかしいけれど、ある意味、だからこそおもしろいのかもしれない。 時代や状況にへつらうのもいやだけど、自分の感性や価値観だけで突っ走ることもできない自分としては、そういう以外ない。 しかし、時代が変わってきて、ようやく若い人々の才能や活躍に目がいくようになったのはいいことだと思う。やっぱり、時代を作っていくのは若い人々なんだから。 こないだ、阿佐ヶ谷スパイダースの長塚圭史さんたちと話していて、つくづくそう思った。あと、角川の青春文学大賞を受賞した『りはめより100倍恐ろしい』を読んだときにもそう思った。 この数年、十代、二十代の才能があちこちにあふれていて、とてもとてもうらやましい。おそらく、社会的にも、そういう才能に注目しようという機運が高まってきているのだと思う。 そういえば、こないだ『幸せな王子』(金原訳)という絵本の絵(というかテクスタイル)を作ってくれたのも、清川さん。しっかり二十代だ。 そういえば、この頃、飲み会なんかにいって、ふと気づくと、まわりはほとんど年下、という状況。 まあ、若者、がんばれといいたい。 年寄りは、若者の邪魔をしないこと。それがなによりだと思う今日この頃である。 2.『アイアンマン』『数をかぞえて』『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』 というわけで、今回はあとがきを三つ。 『アイアンマン』は、『ホエール・トーク』の作者クリス・クラッチャーの作品。『ホエール・トーク』が好きな人には絶対お勧め。 『数をかぞえて』は、ご存じ、デイヴィッド・アーモンドの短編集。 『パーシー・ジャクソン』はアメリカを舞台にした、ユーモラスなモダン・ファンタジー。 というわけで、あとがきを三つ。 訳者あとがき 昨年から集英社の「小説すばる」という雑誌で、「僕が次に訳したい本」というエッセイを連載している。まさにそのままの内容で、訳したい本や訳している本を紹介するコーナーだ。第一回目に取りあげたのが、ダルデンヌ兄弟の新作映画『ある子供』、近松門左衛門の『女殺油地獄』、シンシア・D・グラントの『グッバイ・ホワイト・ホース』、メルヴィン・バージェスの『Doing It』。どうしようもない主人公や登場人物の出てくる青春物をつなげてみたかったからだ。これを書いたとき、第二回目のテーマは決まっていた。クリス・クラッチャーだ。どうしようもなく残酷でやりきれない状況のなかで必死に戦う若者たちを描くクラッチャーの作品をぜひ紹介したかった。 取りあげたのは『ホエール・トーク』『アイアンマン』『Stotan!』。クラッチャーの作品をずらり三冊並べてみた。現代アメリカのヤングアダルト小説のなかで、いま最も気になっているのがクリス・クラッチャーだ。作品数は多くないが、どれも強烈に突き刺さってくる。そして念願がかなって、『ホエール・トーク』(青山出版社)が出て、いよいよ『アイアンマン』が出ることになった。この二作、舞台はワシントン州の差別の激しい町だ。『ホエール・トーク』では、体育会系の運動部員や高校を相手に、母親に捨てられ幼児期のトラウマを抱えたT・Jという少年が戦いを挑む。 そしてこの、『アイアンマン』。 主人公の少年ボーリガードは英語教師のレドモンドに対して反抗的な態度をとったため、〈短気矯正クラス〉に出席する羽目になる。ボーリガードは最初、そんな不良連中のクラスに入ることをいやがるが、指導を受けるうち、次第にとけこんでいく。そして大好きなトライアスロンの大会に向けて毎日必死に訓練を続けた。ところが、まるで天敵のように前に立ちふさがり、ボーリガードをつぶそうとする人間がいた…… ここには、差別やDVや暴力や横暴があふれている世界が容赦なく描かれているが、その世界に振り回されながらも必死に戦う若者たちも鮮やかに描かれている。 それに、登場人物がまたユニークだ。主人公のボーリガード以上にマッチョで、格闘技大好き少女シェリー。カウボーイハットをかぶってやってくる小柄な日系教師ナカタニ。その他〈短気矯正クラス〉のひと癖もふた癖もある連中。 とにかく、半端でない、直球勝負の青春小説だ! 「小説すばる」に書いた第二回目のエッセイの最後の部分を抜粋しておこう。 クラッチャーの作品はスポーツがらみのものが多い。が、どれも、マンガのスポ根物とは違う。主人公(たち)の戦う相手は敵チームではなく、どうしようもなく愚かしい状況や、どうしようもない運命なのだ。そしてまた主人公たちは、そういったどうしようもなさを自分の内に抱えていたりする。そんななかで必死に戦う若者たちを描くクラッチャーの筆は残酷なほどに容赦なく、また優しい。現代アメリカを代表するヤングアダルト作家をだれかひとりといわれば、迷うことなくクリス・クラッチャーをあげる。 最後になりましたが、ナイスサポートの編集者、田中絵里さん、原文とのつきあわせをしてくださった鈴木由美さん、質問にていねいに答えてくださったクラッチャーさんに心からの感謝を! 二〇〇六年二月十七日 金原瑞人 訳者あとがき 翻訳を始めてよかったと思うことは、あまりたくさんない。なにしろ、苦しいだけで、あまり評価されることもないし、まことに地味な作業なのだから。しかし、ひとつうれしいのは、作品をじっくり、ゆっくりかみしめることができるということだろう。まず一読して要約をまとめ、それが出版されるとなると、原文を読みながら訳していく(この作品の場合は、優秀な下訳の人がいるのだが、それでも、味わいながらその訳文に手を入れていく) おもしろいことに、最初に一読したときの印象と、訳し終えたときの印象はかなり違うことが多い。一気に読み切ったときの印象は強烈なのに、読み返し、訳してみるうちに、そのインパクトが弱く弱くなっていく作品というのが確かにある。逆に、読み返し、訳しているうちに、ぐいぐい引きつけられ、いよいよのめりこんでしまう作品というのもある。 デイヴィッド・アーモンドの『火を食う者たち』を読んだときが、まさにそうだった。アーモンドといえば、『肩胛骨は翼のなごり』『闇の底のシルキー』『秘密の心臓』『ヘヴンアイズ』といった、舞台も設定もなんとなくファンタスティックな作品がまず頭に浮かぶ。ちょっと不思議で、かすかにグロテスクで、たまらなく魅力的な空間で、のびやかにつむがれていくみずみずしい物語、といった感じだろうか。まさにユニークな、アーモンド以外だれにも造れない宇宙が息づいている。 ところが『火を食う者たち』には、そういうった幻想的な要素はまったくない。キューバというカリブの小さな島国のミサイル基地をめぐって、アメリカとソビエトが衝突し、あわや第三次世界大戦、という状況そのものがファンタスティックといえばいえなくもないが、反面、残酷で悲惨な現実だった。そんな世界的な状況のなか、イギリスの片田舎で、横暴な教師との対立、父親の病、友だち、といった現実的な問題で悩み傷つきながらも、必死に現実に立ち向かい、父親のために、友だちのために、残酷な先生のために、そして世界のために祈る少年の姿は、とてもとてもリアルだ。そして読む人の心を大きく揺り動かす。 アーモンドから、それまでのアーモンドらしさを一切はぎとった、『火を食う者たち』という作品は、アーモンドの作家としての力をまざまざと見せつけてくれた。最初にざっと読んだときには、いい作品だなと思った程度だったのだが、訳していくうちに、身動きができなくなって、気がつくと、その世界に引きずりこまれてしまっていた。そして、なにより不思議なのは、一九六二年の世界が自分の世界と恐ろしいほど重なっていくことだった。それと同時に、主人公の男の子と自分がいつの間にか、ぴったり重なっていく。その切なさったらない。アーモンドって、なんて作家なんだろうと思ってしまう。 そのアーモンドが今度は、少年の頃の思い出をもとに、短編集を書いた。『火を食う者たち』より、さらにリアルな作品だ。舞台はいうまでもなく、一九六〇年代の北イングランドの小さな炭鉱町フェリング。少年時代の夢、希望、悲しみ、切なさ、そして愛を、ひかえめな言葉でつづった作品だ。どれもがすべて、力強く、優しく、どことなく不思議で、魅力的だ。ファンタスティックな要素はまったくない。 ここにはアーモンドの作品のエッセンスがある。おそらく、アーモンドの作品を読んだ人には、あちこちにそのモチーフが隠れているのがわかるはずだ。彼の創作の原動力になっている記憶の断片、とぎれとぎれの思い出、死ぬまで忘れられない喪失の記憶、そういったものが詰まっている。 もしかしたら、後生、アーモンドの代表作として残るのはこれなのかもしれない。 この『星を数えて』という短編集は、英語版の Counting Staras に収められている短編に、Built-up Sole という短編(Where Your Wings Were という作品集に収録)が加わっている(面倒なことに、Where Your Wings Were という短編集は Counting Stars からの抜粋なのだが、ひとつこの短編が付け加わっている) 日本のみの特別ヴァージョンだ。 どうか、アーモンドの原点を楽しんでほしい。 最後になりましたが、編集の松尾亜紀子さん、翻訳協力者の舩渡佳子さん、細かい質問にていねいに答えてくださった作者のアーモンドさんに、心からの感謝を! 二〇〇六年二月十三日 金原瑞人 訳者あとがき 転校するたびに退学処分になってしまう問題児、パーシー・ジャクソンは、校外授業でメトロポリタン美術館に行くことになった。ところが、引率の先生がいきなり、コウモリの翼とかぎづめを持つ老婆に変身。パーシーが驚いていると、仲の良かったブラナー先生がやって来てボールペンを投げてくれた。パーシーが受け取ると、ボールペンは青銅の剣に変わった…… この悪夢のような出来事のあと、次々に不思議なことが起こるようになり、やがて、パーシーは自分がギリシアの神の血を引いていることを知る。そして、そういう子どもばかりが集まる訓練所でいろんなことを教わるのだが、神々の陰謀に巻きこまれ、思いも寄らない冒険の旅に出発することになる。 さあ、いよいよ、「パーシー・ジャクソンとオリュンポスの神々」シリーズの一作目『盗まれた雷撃』のはじまりだ。 パーシーの父親は神だというが、いったいだれなのか、お母さんはほんとうに死んでしまったのか、ゼウスの雷撃を盗んだのはだれか、そういった謎が渦巻くなか、パーシーは命がけの旅にでる。そしていったん出発したが最後、ねらわれ、襲われ、痛めつけられ、休む間もなく危機にさらされる。しかしサテュロスのグローバー(ちょっと頼りない)や、女神アテナの娘アナベス(パーシーとちょっとそりが合わない)の助けを借りながら、魔物や怪獣や神々の攻撃をすりぬけ、計画の裏をかき、謎の核心に迫っていく。 まさに、スリルとアクションと謎解きのおもしろさが、ぎゅうぎゅうにつまった大スケールのアメリカン・ファンタジーだ! なにより、設定が楽しい。あのギリシアやローマの神々が、いまやアメリカに引っ越してきていて、神々が集うオリュンポス山は、エンパイアステートビルの六百階、雲の上にぽっかり浮かんでいる。それに、ギリシア神話よりもさらに人間的な神様たちも魅力的でユーモラスだ。禁酒中で、皮肉ばかり口にする酒の神ディオニュソス、大型のバイクを乗り回すマッチョな軍神アレス、その他、ハデス、ゼウス、ポセイドン…… とにかくおもしろいファンタジーが読みたいという人は、ぜひ! 20世紀フォックス社による映画化も決まっている。シリーズ第二作目も、今年の四月には刊行予定とのこと。 作者のリック・リオーダンは数々の賞を受賞しているミステリ作家で、日本でもおなじみだが、ヤングアダルトむけのファンタジーはこれが初めて。 最後になりましたが、編集の中村宏平さん、原文とのつきあわせをしてくださった西本かおるさんに心からの感謝を! 二〇〇六年二月十六日 金原瑞人 3.あとがき大全のあとがき じつは、一週間ほど四川省の成都にいってきた。 食べ物はおいしいし、お酒もおいしいし、適度に不潔だし。とてもよいところだった。これから世界のどこにでも住ませてやるといわれたら、中国語を習って、成都にいくかもしれない。 詳しいことは、そのうちHPに書きます。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
|