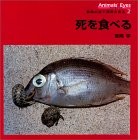 表紙をめくると、いきなり扉にペットの墓地でお供えを横取りする野良猫の、鋭く威嚇的な姿。見るものを挑発するような圧倒的な存在感に、この本のメッセージが託されているようだ。
表紙をめくると、いきなり扉にペットの墓地でお供えを横取りする野良猫の、鋭く威嚇的な姿。見るものを挑発するような圧倒的な存在感に、この本のメッセージが託されているようだ。車にはねられた一頭のキツネ。死が確認されると、体温のうせた体から続々とダニがはい出してくる。死骸(しがい)には用はないというわけだ。ハエが飛んできて、目元や口の柔らかい部分にたかって卵を産み付ける。スズメバチが肉を突っつきに来る。ウジが腐った内臓を食べ、毛皮を食い破って溢れ出す。死骸が見えなくなるほどのウジの大群には圧倒される。写真ならではの迫真力だ。ハクビシンがきて、ウジを食べる。イノシシが残った肉を食う。
キツネの死骸は、さまざまな生き物たちに食べ尽くされ、骨だけになる。酷薄な現実の中に、自然の摂理を読み取るカメラマンの目が鋭い。
ヤブキリの死骸には、アリたちが真っ黒に群がり、砂の中に埋めてバラバラに解体して巣に運ぶ。アマガエルの死骸も、干からびる前にアリたちに湿った土の中に埋められ解体される。さまざまな動物たちの死骸が、生き物たちに食べられ命をつないでいく。人間もまた死をいただいて命をつなぐ。
「動物の目で環境を見る」シリーズの一冊。時間と労力を注ぎ込んだ衝撃的な科学絵本の誕生である。(野上暁)
産経新聞2002.03.26