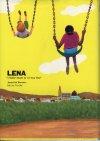 ジャクリーン・ウッドソン『レーナ』(理論社、1998)は、多文化主義の困難に直面させてくれる作品だ。設定自体は、いたってシンプル。「黒人の町」(といっても、炭坑が盛んだった「白人の町」としての歴史は看過できないが)に、レーナという白人の女の子が越してくる。そこで出会うことになるのがマリーという黒人の女の子だ。物語はマリーの視点から、二人がどのようにして出会い、別れることになったかが語られる。二人には、母親がいないという点を除けば、何ら共通点は見当たらない。大学教授を父親にもつマリーとプア・ホワイトであるレーナ。興味深いことに、レーナは「まるで黒人の女の子みたい。もしかすると皮膚の色が薄いだけで、黒人なのかな」と、マリーに思わせるほど黒人らしく描かれている。マリーは言う。「だって黒人の女の子みたいじゃない」。一瞬の静寂の後、レーナは言った。「あたし、白いクズだよ」。レーナの自己同一性と身分証明は、差別する側の価値規範(白人蔑視)に同化することで維持されると同時に示された訳である。しかし、この台詞は、レーナが「黒人」 に漸近できても、決して「黒人」の位置を占めることができないことを彼女が十分に知り尽くしていることをも示している。レーナは「白人のクズ」として自らを表象せざるを得ないのである。したがって、マリーがレーナを「黒人」として表象したこと自体、レーナにとって酷であっただろうし、マリーがそのような限界から出発せざるを得なかったのは致し方がない。もちろん、マリーがレーナに看取したのは、白人という認識枠から零れ落ちる異質性であって、マリーはそれを「黒人らしい」と表現しただけであろう。しかし、「白人らしくない」ことが「黒人らしい」に短絡的に反転されて表象されてしまうところに、レーナの困難があった。「黒人らしくあれ」という要求ほど、レーナに「白人のクズ」でしかない自分を痛感させるものはないのだから。
ジャクリーン・ウッドソン『レーナ』(理論社、1998)は、多文化主義の困難に直面させてくれる作品だ。設定自体は、いたってシンプル。「黒人の町」(といっても、炭坑が盛んだった「白人の町」としての歴史は看過できないが)に、レーナという白人の女の子が越してくる。そこで出会うことになるのがマリーという黒人の女の子だ。物語はマリーの視点から、二人がどのようにして出会い、別れることになったかが語られる。二人には、母親がいないという点を除けば、何ら共通点は見当たらない。大学教授を父親にもつマリーとプア・ホワイトであるレーナ。興味深いことに、レーナは「まるで黒人の女の子みたい。もしかすると皮膚の色が薄いだけで、黒人なのかな」と、マリーに思わせるほど黒人らしく描かれている。マリーは言う。「だって黒人の女の子みたいじゃない」。一瞬の静寂の後、レーナは言った。「あたし、白いクズだよ」。レーナの自己同一性と身分証明は、差別する側の価値規範(白人蔑視)に同化することで維持されると同時に示された訳である。しかし、この台詞は、レーナが「黒人」 に漸近できても、決して「黒人」の位置を占めることができないことを彼女が十分に知り尽くしていることをも示している。レーナは「白人のクズ」として自らを表象せざるを得ないのである。したがって、マリーがレーナを「黒人」として表象したこと自体、レーナにとって酷であっただろうし、マリーがそのような限界から出発せざるを得なかったのは致し方がない。もちろん、マリーがレーナに看取したのは、白人という認識枠から零れ落ちる異質性であって、マリーはそれを「黒人らしい」と表現しただけであろう。しかし、「白人らしくない」ことが「黒人らしい」に短絡的に反転されて表象されてしまうところに、レーナの困難があった。「黒人らしくあれ」という要求ほど、レーナに「白人のクズ」でしかない自分を痛感させるものはないのだから。本書の最後は、次のような言葉で締め括られていた。マリーの耳に「あたしたち、みんな同じ人間じゃないの」というレーナの声が聞こえてくる。そしてマリーは思う。「それなのにさ、どうして、みんな同じ人間でいられないんだろうね?」。何故にマリーは(空想上の)レーナの言葉をかくも否定しなければならなかったのだろうか。この一文は様々に解釈できるが、書評子は積極的に評価したい。というのも、人間主義(ヒューマニズム)は人種差別を克服するどころか、往々にして隠微にレイシズムを温存するからである。人間主義は「人類」というメタレヴェルを設定するが、そのメタレヴェルそのものが「白人/黒人」というオブジェクトレヴェルでの差別に根拠を与えてしまう。換言するならば、レイシストは「人類」という土俵なくして差別を遂行できないのである。ヒューマニストとレイシストの差異は、「人類」の中に「白人」と「黒人」という二つの「種」を設けた上で両者の力関係を均衡にあるいは不均衡に配分するのかという量の問題に収斂される。だからこそマリーは、「それなのにさ、どうして、みんな同じ人間でいられないんだろうね?」と言うことで、「人類」という「類 」の中に「白人」と「黒人」という二つの「種」があって、二つの人種が「人類」の名のもとに理解し合う図式を否定したのである。繰り返すが、彼女が拒否したのは、二人が理解/誤解し合う可能性ではなく、自分たちを「人間」というメタレヴェルにおいて了解してしまうような姿勢ないしは認識の仕方であった。あれほ
ど人種差別に直面していたレーナでさえ(だからこそ)陥りかけた人間主義のトラップは、容易に復活するのである。もちろん、人間主義を否定したからといって何かが解決された訳ではない。しかし、少なくとも、人間主義のように安易に「人種」を超えてしまうことでレイシズムを無毒化するという最悪の事態は回避されているように思う。
蛇足ながら、みすず書房から昨年(1998)、フランツ・ファノン『黒い皮膚・白い仮面』(復刊)とガヤトリ・C・スピヴァク『サバルタンは語ることができるか』の両著が刊行されたことを併記しておきたい。前者はレーナにおけるアイデンティティ・ポリティクスの問題、後者はレーナを語るマリー(>作者>読者)が直面していた表象の政治学を考えるのに格好のテキストであるからだ。興味のある方は、一読されたい。(書き下ろし/3.26.99/目黒強)