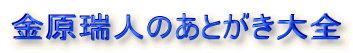
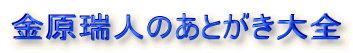
|
1.今回、あとがきはひとつだけ 12月29日に出たアレックス・シアラーの『世界でたったひとりの子』(竹書房)のあとがきを。 訳者あとがき 『ミッシング』のあとがきでも書いたが、シアラーは書くたびに、題材もテーマも変わる。今回はSFだ。舞台は、そう遠くない未来、老化を防ぐ薬が発見されて、だれもが若くいられるようになった時代だ。平均寿命は百五十歳くらいで、二百歳を越える人もいる。ところが人々が若いまま長寿になった結果、ほとんど子どもができなくなってしまった。 主人公はタリンという少年。両親はいなくて、ディートという男が親代わり……といっても、ディートは養い親というだけではなくて、タリンを使って商売をしている。子どものいない人々に、タリンを一時間いくらで貸して、もうけているのだ。子どもは、ほとんどいない世界だ。高い金を出して、タリンを借りたい人間はいくらでもいる。 しかしタリンもあと数年で子どもではなくなってしまう。そこで、ディートはタリンに、PPインプラントという手術を受けさせようと考えている。これは死ぬまでずっと子どものままでいられるという手術だ。ディートはこういう。 「PPは子どものうちに受けなきゃだめだ。おとなになってからじゃ意味がない。そのときには手遅れだ。なあ、おまえ、どう思う? どうだ? PPを受けてみるってのは? 金なら出してやる。そうすれば、俺たち、一生、楽に暮らせるんだからな。おまえと俺のふたりでさ。金は、おまえのかせぎから返してくれりゃあいい」 実際、PP手術を受けて、子どものままの姿形でタリンのような仕事をしている人もいるし、ショーで踊ったり歌ったりしている人もいる。ただ、この手術を受けたら、それきり成長が止まってしまう。 タリンはそんなのはいやだと思い、逃げようかとも考えるが、ディートは抜け目のない男で、なかなかすきをみせない。それに、まわりはほとんど大人しかいない。そんななかに子どもがひとりで飛びだしてしまったら、目立たないわけがない。それに、子どもをさらって大もうけしようとたくらんでいる人間もたくさんいるはずだ。事実、タリンを誘拐しようと追っている男もいる。 タリンはどんどん追いつめられていく。しかし、逃げようがない。逃げようがないまま、PP手術が迫り、あやしい影が忍び寄ってくる…… この本を読んだときは、まずこの世界にぞっとしてしまった。ディートはこんなふうにいう(この男、ある意味、冷血な人間だが、人を見る目も世界を見る目も、驚くほど鋭い) 「この世は、だれでもない人間であふれてる。どいつも、動かなくなった時計みたいな顔をしてやがる。ちょっとあたりを見まわして、自分の目で見てみろ。みんな四十になると、老化防止薬を飲みはじめる。それで、どいつもこいつも同じ顔になる。まるで、ろう人形だ。凍りついたほほえみに、不自然な肌の色。どう思うかって? これは世界の復讐さ」 「年寄りじみたふるまいもしない。いつだって最新のファッションに身を包んでやがる。だがな、中身は化石さ。肝心な中身はもう灰になる寸前ってやつらだっている。あの老化防止薬はな、人間が外から腐っていくのは食いとめるが、中からの腐敗は治せないんだ。おきまりの『生きるのは飽きたが、死ぬのは怖い』病にかかったらおしまいさ。それに効く薬はないからな」 この世界のなかで、金のことしか考えていない男にしばられているタリン。タリン自身、それがいやで、なんとかしたいと思ってはいるものの、自分が本当にどうしたいのか、どうすればいいのか、まったくわからない。だけど、大人になりたい。しかし逃げ場はどこにもない。やがてディートがPPのことを真剣に考え始める。 このタリンの恐怖、孤独が痛いほどに突き刺さってくる。作者は、どこまでもどこまでもタリンを追いつめていく。 読み終えて、思わずほっとため息をついてしまった。切なさ、悲しさ、孤独、絶望、そういったものが渦巻くなか、最後にそっと…… どうか、タリンといっしょに、そう遠くない、この未来世界を旅してみてほしい。この世界の恐怖を、タリンを襲う恐怖を味わってほしい。そして、死について、老いについて、若さについて、なにより生について考えてみてほしい。 きっと、忘れられない一冊になると思う。 (作品中、二度ほど出てくる「ポッド」というのは、地下鉄に似た未来の乗り物のこと) 最後になりましたが、編集の中山智映子さん、翻訳協力者の小田原智子さん、原文とのつきあわせをしてくださった杉田七重さん、そして質問に快く答えてくださった作者のシアラーさんに、心からの感謝を! 二〇〇五年十一月二十九日 金原瑞人 2.長寿 じつは、このところ、長寿がらみの本が多い。ひとつは、この『世界でたったひとりの子』、もうひとつは『大吸血時代』(そのうち求龍堂から出版の予定)。両方とも、長寿の世界が舞台。で、両方とも、長寿なんてちっともいいことない、という話。『たったひとりの子』のほうは、あとがきにも書いたけど、もう一度、引用。 「年寄りじみたふるまいもしない。いつだって最新のファッションに身を包んでやがる。だがな、中身は化石さ。肝心な中身はもう灰になる寸前ってやつらだっている。あの老化防止薬はな、人間が外から腐っていくのは食いとめるが、中からの腐敗は治せないんだ。おきまりの『生きるのは飽きたが、死ぬのは怖い』病にかかったらおしまいさ。それに効く薬はないからな」 いつもながら、シアラーって、こういう科白がうまい。 また『大吸血時代』のほうも、みんな吸血鬼になって、ほぼ不老不死。日光にあたるか、体の原型が残らなくなるほどのことにでもならない限り、死なない。主人公が吸血鬼を(よみがえれないように)殺す場面があるんだけど、その吸血鬼は、「ありがとよ」といって死んでいく。 だよなだよな。やっぱり、そうだよなと思っていたら、「歌う生物学者」本川達雄の『「長生き」が地球を滅ぼす:現代人の時間とエネルギー』(阪急コミュニケーションズ)という本が出た。これはすごい本で、まさに現代人必読、なのだ。 まあ、詳しいことは書かないけど、『世界でたったひとりの子』『大吸血時代』『「長生き」は地球を滅ぼす』と立て続けに、似たようなテーマをはらんだ本にぶつかり、ついつい長寿について考えてしまった。そのへんは、いずれまた、ゆっくり。 3.恐怖短編集(英米編) 12月、赤木かん子から、6巻か7巻の「恐怖短編集」をポプラ社から出す予定で、そのうちの「英米編」を担当しろという連絡があった。つまり、短編をいくつか選んで、それに前書きを書けとのことらしい。 というわけで、まず次の作品を選んでみた。 恐怖小説アンソロジー(英米古典編) ・小壜の悪魔 スティーヴンソン The bottle imp (1893) by Robert Louis Stevenson ・信号手 ディケンズ No 1 Branch Line: The Signalman ・告げ口心臓 ポー The Tell-Tale Heart by Edgar Allan Poe ・アウルクリーク橋をめぐるできごと ビアス An Occurrence at Owl Creek Bridge by Ambrose Bierce ・闇の海の声 ホジスン The Voice in the Night by William Hope Hodgson 以上5編で、原稿用紙にして約200枚。ちょうど、長さとしては手頃。選んだ理由はというと、昔から好きだったから。ただ、ポーについては『モルグ街の殺人事件』(岩波少年文庫)でいくつかの短編を訳したので、そこに載っていないものを選んだ。 この5編。いままでの訳をもらってくるよりは、新訳のほうがいいだろうと、4人にお願いした。まあ、だれがどれを訳しているかは、お楽しみに、刊行を待ってほしい……が、そのうちのひとりは、野沢さんで、担当の作品はアンブローズ・ビアスの「アウル・クリーク橋」。 この作品の翻訳をめぐって、ちょっとおもしろいことがあったので、野沢さんにまとめてもらった。翻訳に興味のある人はぜひ読んでほしい。 4.アウルクリーク橋をめぐるできごと アンブローズ・ビアスの短編小説、”An Occurrence at Owl Creek Bridge”を訳すことになり、原文を一読して、「うぅ……」とうなった。南北戦争のさなか、民間人ながら愛する南部諸州のために英雄的な貢献をしたいと考えた男が、あることを企て、北軍に捕まり、鉄道橋で絞首刑にされて……という、緊迫感あふれるストーリーなのだが、私の三大苦手要素、「戦争」「アクション」「空間把握能力に乏しいと理解できない情景描写」が、短い作品のなかにぎっしり詰まっているのだ。しかし、嘆いても始まらない。いつものように地道に辞書をひきつつ原文を精読し、所々悩みながら訳し、訳文を原文とつきあわせ、推敲し、既訳作品(岩波文庫の『ビアス短編集』に所収のもの)と読みくらべて誤訳がないかチェックし、最後にもう一度推敲してから、監訳の金原先生のもとへ訳稿を送り、ふうっと息をついた。三十枚ほどの短編なのに、とても時間がかかった。 数日後、金原先生からアカ入りの訳稿とともに、「インターネットにも『アウルクリーク橋でのできごと』の翻訳が載ってるよ」という情報が送られてきた。http://f59.aaa.livedoor.jp/~walkinon/owlcreek.htmlで公開されているという。さっそく読んでみると、訳者は実名を伏せているがかなりの英米文学通で、翻訳も勉強された方らしく、正確でしっかりした訳文だった。この方(仮にX氏と呼ばせていただく)は、訳文に添えた「翻訳ノート」のなかで、岩波文庫に収められた翻訳の誤訳を指摘している。問題の箇所は作品の最後の部分で、原文は以下のとおり。(ここからはネタバレになるので、物語の結末を知りたくない方は先に作品をお読みください。原作の全文はhttp://www.gutenberg.org/dirs/etext95/owlcr11.txtで読むことができます) Peyton Farquhar was dead; his body, with a broken neck, swung gently from side to side beneath the timbers of the Owl Creek bridge. 岩波文庫の訳は下記のとおり。 ペイトン・ファーカーは死んでいた。首の折れた、彼の体は、アウル・クリーク鉄橋に流れ集まった材木の下で、右に左にゆっくりと揺れていた。 X氏は、「たしかに作品半ばに、洪水で運ばれてきた流木が鉄橋にたまっているという記述があるが、その『流木』にはdriftwoodという単語が使われており、この最後の部分に出てくるtimbersを『流木』ととらえるのは無理がある」と述べ、次のように訳していた。 ペイトン・ファーカーは死んだ。首の折れたその死体は、アウル・クリーク鉄橋の横木の下で、左右にゆっくり揺れていた。 ちなみに私も、timbersを「流木」と解するのに反対、という点ではX氏と同意見だが、次のように訳していた。 ペイトン・ファーカは死んでいた。首の折れたその死体は、そっと左右にゆれながら、アウルクリーク橋の枕木の下にぶらさがっていた。 さて、ここで私は迷路に入りこんでしまった。原因は、X氏が使った「横木」という訳語である。じつは、作品の冒頭に次のような文章がある。 A rope closely encircled his neck. It was attached to a stout cross-timber above his head and the slack fell to the level of his knees. 死刑にされようとしている男の様子を描写した部分だが、ここに出てくるcross-timberとは、おそらく橋の上部に横に渡されている木材のことだろうと思い、建築士の夫を持つ友人にメールできいて、専門的には「梁」と呼ぶのだと知り、しかし読者が小中学生ということもあって、金原先生にも相談した結果、「横木」という訳語にたどりついていたのだ。そして、X氏が最後の部分のtimbersを「横木」と訳しているのをみたとき、なぜか私の頭の中に、「あれ? 死体は橋の上部の横木の下にぶらさがっているのであって、枕木の下まではいってないのかも。脚ぐらいは橋の下に落ちてるかもしれないけど、全身が橋の下にぶらさがってるわけではないのかも」という疑問が、たちまちぶわーっと広がってしまったのだ。自分が何を根拠にtimbersを「枕木」と訳したのかも忘れ、ただもう、「timbersって何? 死体はどこにぶらさがってるの? 橋の上なの下なの?」という堂々めぐりに陥り、お忙しい金原先生にまたも質問のメールを送ってしまうという体たらくだった。しかし、ある朝、新しい頭で原文を読み直してみて、やはり死体は枕木の下まで落ちていると確信するに至った。その根拠はふたつある。 (1) 枕木に渡された足場の板が外れて、首に縄を巻かれた男が落ちていくときの描写が、As Peyton Farquhar fell straight downward through the bridge となっている。throughというからには、全身突き抜けているのではないか。 (2) 先に引用した冒頭の文章に、「たるんだ縄が男の膝のあたりまで垂れている」とある。一端を橋の上部の横木に、もう一端を首にゆわえつけられた縄が膝まで垂れているということは、少なくとも首から膝までの長さの二倍分、縄が余っていて、ぴんと張ったときには首から膝までの長さの二倍分、首が下へいくということだ。私の首から膝までは、メジャーで測ったら一メートル近くあった。つまり、首が二メートル下がるんだから、橋の下までいくはずだ。 空間把握能力に恵まれた方にとって、上記(2)の考察はあまりにばかばかしいかもしれないが、どうか忍耐と同情をもって読み飛ばしていただきたい。 ここでもう一度初心にかえって、timberを辞書でひいてみた。『リーダーズ英和辞典』には、「建物」「建材」「構造木材」「フレーム材」などと載っている。『ランダムハウス英語辞典』には、「(構造体の一部を成す)一本の木材(梁、桁、垂木、柱など)」とある。 そうか、橋の上部の「横木」も下部の「横木」も、橋桁も橋脚も、みなtimberなのであって、最後のtimbersは構造体としての橋全体をさしているのかもしれない……と、ようやく自分なりの結論に近づいた頃、金原先生から、「アメリカ人の同僚にきいてみたところ、When I read this, I imagine that "the timbers" refers to the frame of the bridge.という返事がきた」というメールをいただいた。やはりそうか。ここでもう一度、X氏の「翻訳ノート」を読み返してみると、「冒頭のtimberが単数なのに対し、最後のtimbersは複数なので、別の意味と考えられる。後者はこの橋のフレームと考えてよいのではないだろうか」と書かれている。なんと私は、「横木」という訳語にとらわれて、X氏の文章も辞書の定義も、ちゃんと読んでいなかったのだ。翻訳者として、最低。また、最初から作品に対する苦手意識があったため、つい師匠に頼ったり、既訳作品に必要以上に影響された。さらに、数年前までは英会話学校に通ってネイティヴ・スピーカーの先生に原書のわからないところをきいたりしていたのに、最近はそういう努力も怠っていた。『アウルクリーク橋でのできごと』はもしかしたら、翻訳の神様が、最近たるんでいる野沢に活を入れるべく与えられた、ささやかな試練だったのかもしれない。 結局、最後の部分の訳は、「アウルクリーク橋の下にぶらさがっていた」という、きわめてシンプルなものに落ち着いた。 ここで、『アウルクリーク橋でのできごと』に関して、トリビアルな情報をふたつほど。まず、この作品は『ふくろうの河』というタイトルで1961年にフランスで短編映画化されており、カンヌ映画祭で短編グラン・プリを受賞している。残念ながらビデオにもDVDにもなっていないが、意外に根強い人気があるらしく、日本でも頻繁に自主上映されている。もうひとつは、角川ホラー文庫に『吊された男』という、首つりの話ばかり集めたアンソロジーがあり、ビアスの『アウルクリーク橋でのできごと』も収められている。こちらの訳はどうだろうと気になり、購入してみたら、岩波文庫と同じ訳だったが、なんと訳者名が誤植されていた(名字のなかの「津」が「澤」になってしまっている)。 最後に、冒頭で「苦手三大要素」を告白してしまったので、いちおう「得意三大要素」も記させていただくと……「恋」「少年」「ああでもないこうでもないと悩んだり、妄想にふけったりする人物の心理描写」といったところです。あと、「旅」、「わがままな少女」、「タフなおばあちゃん」、「異文化や環境の激変の中で悪戦苦闘する人物」なんかも好きだし……と、きりがなくなりそうなので、このへんで。 5.ビアスについての蛇足 この短編、たしかに英語はとても難しいのだが、とてもおもしろい。芥川龍之介もビアスが大好きで、かなり影響を受けている。 それから、スタンリー・エリンの『特別料理』にも、ビアスがちらっと出てくる。興味のある方は読んでみてほしい。 6.さて八重洲座 八重洲座の企画、今年は奇数月は女流義太夫、偶数月は落語と決まった。映画のチケット一枚分程度で、一流の古典芸能を楽しんでもらおうという企画。ぜひぜひ、遊びにきてほしい。詳細は金原のHPへアクセスください。 1月は27日(金)。 |
|