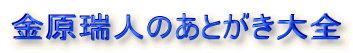
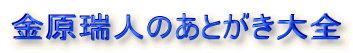
|
あとがき大全(55回目) 1.長寿 本川達雄という人は、とてもおもしろい人で、名著『ゾウの時間、ネズミの時間』で有名になってから、次々におもしろい本を出してくれている。 『12歳からの読書案内』(すばる舎)でも紹介した『歌う生物学、必修編』(阪急コミュニケーションズ)は、斬新で正確な歌でもって、生物学を学ぶという、信じられないような本で、なんと本川先生ご自身が歌っているCDもついている。もう、買うしかないでしょう。 その本川先生の『「長生き」が地球を滅ぼす:現代人の時間とエネルギー』は、タイトルからいってすごい。それに帯には「ゾウもネズミも心臓は15億回打って止まる。哺乳類共通の法則を人間に当てはめれば、ヒトの寿命は26年」! あるインタビューで、人間の寿命についてたずねられ、「生物学的にいうと、生殖が終われば、生物の存在価値はないんです」といってのける。 しかし先生はそういいながらも、とても優しい。 とはいっても、人間はどんどん寿命をのばしてきたわけだから、この長生きの人間がどうすればいいかということをちゃんと考えてくださるのだ。 だから、もちろん、『「長生き」が地球を滅ぼす:現代人の時間とエネルギー』という本、年寄りは死ねという内容ではない。そうではなくて、長く生きすぎている人間は、さて、どうしようか、という、自分もふくめて(ご本人、団塊の世代)論じた前向きの本なのだ。 そしてこの本のもうひとつの論点は、時間ってなんなんだ、ということ。 普通の感覚でいうと、時間というのは直線的で、あともどりできない、不可逆的なものだろう。しかし、アボリジニやネイティヴ・アメリカン(アメリカ・インディアン)なんかは、時間を円還的にとらえている。本川先生によると、前者は物理的時間、後者は生物的時間ということになる。 現代人はこの物理的時間、直線的時間にとらわれてしまって、生きる意味や生きる価値を見失っているのではないか。 じっくり冷静に考えれば、いまの世界がこのまま進んでいった、その先にいったい何があるのか、不安がないはずがない。 この本、時間のほかにもいろんな問題をつきつけてくれる。たとえば、人間の密集度。 ちょっと引用してみよう。 電車の人口密度は、いったいどの程度なのでしょう? 電車に定員の三倍乗っているとすると一平方メートルに八人ほどで、これはヒトサイズの動物の密度の五八〇万倍になります。 これほど密に住んでいる哺乳類の体重はどうかと計算すると〇・〇〇二グラム。じつはこんな小さな哺乳類は存在しません。一番小さいトガリネズミでも体重二・五グラム程度です。それより三桁も小さいのです。〇・〇〇二グラムといえば蚊のサイズです。 ストレスを感じるのも無理はないと思う。 ともあれ、まずは、読んでみてほしい。 ついでにその参考書を。 『世界でたったひとりの子』(アレックス・シアラー)竹書房 『大吸血時代』(デイヴィッド・ソズノウスキ)求龍堂 2.あとがき 『世界でたったひとりの子』は前回に載せたので、今回はまず、長寿がらみで『大吸血鬼時代』(表紙が抜群にいいです)。それからホリー・ブラックの『犠牲の妖精たち』とジェラルディン・マッコクランの『世界はおわらない』(装幀が抜群にいいです)を。 ほかに清川あさみさんの絵(というか、テクスタイル)による絵本『幸せな王子』(リトルモア)があるんだけど、これはあとがきなしなので。とはいえ、とてもきれいな絵本です。 訳者あとがき(『大吸血鬼時代』) 吸血鬼物というと昔からありそうだが、イギリスでの本格的な吸血鬼小説は、ジョン・ポリドリの『吸血鬼(ヴァンパイア)』(一八一九年)あたりが最初といわれている。謎の貴族ルスベンに興味を抱いた青年が、ルスベンとともに旅をするうち、次々に恐ろしい事件に遭遇するといった筋書きだ。それからレ・ファニュの『吸血鬼カーミラ』(一八七二年)。これはドイツが舞台で、ある城にカーミラという名前の貴族の娘がやってくるところから話が始まる。女の吸血鬼物で、ある種官能的な彩りもあり、ロジェ・バディム監督がこれを原作に『血とバラ』を撮っている。そしてついにブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』(一八九七年)の登場。いうまでもなく、吸血鬼物の決定版だ。 これ以降、多くの吸血鬼小説が書かれる。また映画も芝居も次々に作られていく。そして二〇世紀の恐怖小説、ホラーに吸血鬼は欠かせない存在となった。スティーヴン・キングも『呪われた町』を書き、アン・ライスも『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』をはじめ数々のヴァンパイア物を書いている。また英米では、ヴァンパイア物とヴァンパイア・ハンター物はほぼ毎月のように出版されている(ヴァンパイアがらみのロマンス小説までシリーズで出ているくらいだ)。 一九世紀に誕生し、成長した「吸血鬼」は、いまや人間によって、しゃぶりつくされ、吸いつくされているといっていい。 いってみれば、現代は「吸血鬼小説」にとってあまりいい時代とはいえない。もうほとんど、ヴァリエーションらしいヴァリエーションは出つくして、どこをどうひねったところで、ユニークで新鮮な作品はできそうにないのだ。せいぜい、エロティックな色をつけたり、サイコホラー風にしてみたり、残酷描写をちりばめてみたり、ロマンチックに描いてみたり、ボーイズラブ風に仕上げてみたりと、そのくらいだろう。ちょっと目端のきく作家なら、吸血鬼なんてものには見向きもしない。 ところがそんななかから、二一世紀、こんな吸血鬼小説が飛びだした! 『大吸血鬼時代』(Vamped)、これを読んだときは、ううん、こんな手があったかと、思わずうなってしまった。作者のデイヴィッド・ソスノウスキ、新人とはいえ、ただ者ではない。 発想、着想、構想、展開、結末、すべてにおいてユニークで新鮮で斬新、かつ登場人物・登場ヴァンパイア、すべてキャラが立っていて、魅力的で、クール。 舞台は近未来、というか、パラレルワールド。世界で吸血鬼革命(戦略?)が成功して、ほとんどが吸血鬼という世界。人血をすすれなくなったヴァンパイアたちはスーパーでパック入りの人工血液を買ってきては、それを飲んで、ごく普通に働いている。もちろん、不老不死。日光にさらされたり、身体の原型がなくなるようなことにでもならない限りは、だいじょうぶ。人間はほぼ絶滅状態……なのだが、じつは裏の社会には「人間牧場」というものがあって、そこでは「生きた人間」を飼育して、金持ちや有力者に提供している。 その人間牧場から脱走した母親と娘がいた。深い穴を掘ってそこで暮らしていたところ、やがてヴァンパイアに見つかり、母親は虐殺されてしまうが、娘のほうは逃げのびる。その娘を拾ったのが、この作品の主人公マーティ。もちろんヴァンパイア。いきなりこの娘にパン切り包丁で腹を刺されてしまう。しかしヴァンパイアなので傷はすぐに癒えていく。 さて、マーティはこのいかにもおいしそうな人間の娘をどうするか、というと、あれこれ考え、悩んだ末に、育てることにする。しかしヴァンパイア界で、ほとんど存在しないはずの人間の子どもを育てるというのは、非常に難しい。次々に難問、奇問がマーティを襲う。が、マーティは次々に、それをクリアしていく……が、それだけではない。イスズという日本車の名前をもつ娘もまた、様々な問題を突きつけてくる。が、マーティは様々な方法でそれを回避し、やがて、ふたりの間には……というふうな展開になるかどうかは、さて、読んでのお楽しみとしておこう。 以上の説明でわかってもらえたと思うが、これは恐怖小説ではない。簡単にいってしまえば、十年くらい前に流行ったPCゲーム『プリンセス・メーカー』のヴァンパイア・ヴァージョンであり、また特異な状況における、とてもリアルな子育て小説、といったところだろうか。 いたるところに、ユーモアとウィットと皮肉がちりばめたれた、この吸血鬼版父娘の物語、涙と笑いなしには読むことができない。 またあちこちにちりばめられたエピソードも辛辣だ。たとえば、ローマ法王の妹が、アメリカから電話をかける。 「エイズになったんだけど、どうしよう。選択肢はふたつ。このまま死ぬか、ヴァンパイアになって生きのびるか」 当時、ローマカトリックは、裏でヴァンパイア狩りをしていた。さて、法王の答えが知りたくなったら、この本を読んでみてほしい。 この作品のエンディング、これがまた素晴らしい。この長い作品の最後にたどりついたときの感動、それも保証しておこう。 最後になりましたが、編集の深谷路子さん、原文とのつきあわせをしてくださった鈴木由美さん、細かい質問にていねいに答えてくださった作者のデイヴィッド・ソスノウスキさんに心からの感謝を! 二〇〇六年一月十日 金原瑞人 訳者あとがき(『世界はおわらない』) すさまじい洪水にぽつんとひとつだけ浮かぶ箱舟。いったいそのなかでは、何が起こるのだろう。そしてそのまわりでは……? ジェラルディン・マッコクランの『世界の終わり?』(Not the End of the World)を読み終えたときは、あまりに快い読後感に、ふっとため息がもれた。 その途方もない世界の広がりと、目の前に見えるようなリアルな描写と、次々にこちらの予想を裏切ってくれる巧みな物語に翻弄されて、文字通り、舵のない船で洪水のなかを思うがままに引き回されてしまったのだが、エンディングがとても魅力的なのだ。 登場人物はまず、家長のノア、長男のシェム、次男のハム、それぞれの妻、末っ子のヤフェト(十二歳)。それからヤフェトの妻にと強奪されてきたツィラ。そしてもうひとり、聖書には出てこない、ひとり娘のティムナ。この物語のほとんどはこのティムナが語ることになる。 豪雨が降り始め、洪水のなかを流されだすと同時にいきなり激しい場面になる。箱舟にすがりつく人々を、シェムとハムが棒でなぐり落としていく。そして信心深い人々まで、溺れるがままに見捨てていく。ティムナは不思議に思う。神は、人を愛せとおっしゃったはずなのに。しかし父親のノアは、あれは悪魔がここに乗りこもうとしているのだという。本当にそうなのだろうか。ティムの心に深く重い疑問が残る。 一方、ヤフェトの妻にと無理やり連れてこられたツィラは、この狂信的な一家とはなかなかなじめない。そしてヤフェトもまた、生まれつきの気弱さもあって、おろおろするばかりだ。 そんなときのことだ。 あたしがそれを見たのはその時だった――一本の木の大枝が船尾材にひっかかっていた。ううん、ひっかかっていたんじゃない。袋か外套でそこに結びつけられていたのだ。 その枝につかまりながら、腕と肩と頭を別にして体を沈めていたのは、女の人だった。肌は紫色だった――流れの中に長く浮かびすぎたプラムみたいに。女の人は、自分の服を使って木を船尾材に結んだにちがいない。でも三日月形の船の跡を運ばれていく間、だれにも声を聞いてもらえずにいたのだ。 木の幹にまたがっているのは、麻のシャツを来た男の子だった。シャツはびしょぬれで、その下の肌の色が透けて見えた。男の子は賢人みたいに座り、目を閉じていた。まつげは雨をたっぷりふくんでいた。表情はほとんどなかった。 そして男の子の腕には、赤ちゃんがいた。 暗くゆるやかに流れてきた物語が、ここで一気に激しく、ドラマチックに動き始める。ティムナはこの男の子と赤ん坊を助けて、船倉にこっそり隠すのだ。 このあと、さらに降り続く豪雨のなか、洪水にもまれながら、物語は物語で一転二転し、思いも寄らない方向へと流れていく。 そしてようやく雨がやみ、最後の最後、素晴らしい世界が、小気味のいい音とともに大きく開ける。 そう、'Not the End of the World' 、この言葉が、新しい意味を持って、新しい希望を持って、響き渡る。最後をしめくくる、渡り鳥たちの語りは圧巻だ。 考えてみれば、聖書のエピソードは、狂信的な家長ノアと、それに服従する息子たちの演じる残酷な神の物語かもしれない。これを素材に、自由な愛の物語を作り上げたマッコクランには、ただただ驚くほかない。 これまで『不思議を売る男』『ジャッコ・グリーンの伝説』と、マッコクランの作品はふたつ訳していて、いまもうひとつ訳している途中なのだが、この人の想像力というか物語力は、すごい。普通の人とはまったく異なった想像力と、それを有無を言わせず納得させ想像させてしまう物語力の両方を兼ね備えているらしい。 この作品は、まさにそんな作者の魅力が凝縮されている。どうぞ、ゆっくり、楽しんでほしい。 なお最後になりましたが、ナイスサポートの編集者浜本律子さん、原文とのつきあわせをしてくださった鈴木由美さん、細かい質問に答えてくださった作者のマッコクランさんに心からの感謝を! 二〇〇六年一月十五日 金原瑞人 訳者あとがき 一九七一年生まれのホリー・ブラック、日本では子どもむけのファンタジー、「スパイダーウィック家の謎」シリーズが出版されているが、この『タイズ』(Tithe)は同じファンタジーながら、ちょっと違う。いや、かなり違う。いや、まったく違う。 それは最初の部分を読んでもらえばすぐにわかるはずだ。 主人公は十六歳のケイ。タバコを吸い、ミルクを飲んでいるうちに、ロックのライヴが終わり、ヴォーカルをやっていた母親がもどってくる。母親はケイからタバコをもらうと、酒臭い息を吐きながら一服する。そこへ母親の彼氏のロイドがやってきて、声をかけ……次の瞬間、ナイフを振り上げる。 「ハリー・ポッター」をはじめとする正義と勇気の正統派冒険ファンタジーのファンは、ここから先には立ち入らないほうがいい。 ケイは母親とふたり、幼い頃を過ごしたおばあさんの家にやっかいになる。そして森のなかで、瀕死の若者に出会う。 片手に反った剣を握っている。それは靄のかかった暗がりの中で、まるで細い新月のように輝いていた。渋い銀色の長い髪が濡れて首筋に張りつき、鋭い輪郭の面長の顔を縁取っている。継ぎ目のある黒いよろいの上を、雨水が細く流れていく。もう片方の手は、胸に突き刺さっている枝をつかんでいた。 木の枝で胸を貫かれた若者は耳がとがっていて、息をのむほど美しかった。妖精だったのだ。妖精はロベインと名乗った。ロベインはケイの手当を受けると、水のなかから邪悪な黒馬ケルピーを呼び出して去っていく。 こうして妖しく危険な闇のファンタジーが幕を開ける。 やがて知らされるケイの秘密、そして犠牲の儀式、妖精たちのあいだでめぐらされる計略と陰謀、敵対するシーリー・コートとアンシーリー・コートの激しい戦い、そのふたつの勢力からまったく独立して暮らしている妖精たちの策謀……それに巻きこまれていくケイと、ケイの仲間たち。そしてなにより、ケイとロベインの運命は……? 死の影があたりをおおい、血の臭いの漂うこの世界、グロテスクで、ちょっとユーモラスで、ぞっとするほど美しい。まるでボッシュか、アーサ・ラッカムか、ビアズレイの絵のようだ。 まさにエッジの立った、危ないモダン・ファンタジー。 子ども立ち入り禁止の、パンクでセクシュアルで、スタイリッシュでファッショナブルな妖精物語。いま最も注目すべき、新感覚のファンタジーといっていい。 なお最後になりましたが、編集の津田留美子さん、原文とのつきあわせをしてくださった鈴木由美さんに心からの感謝を! 二〇〇五年十月二十二日 金原瑞人 3.発音 『犠牲の妖精たち』で、「ビアズレイ」と書いてしまったのだが、正しい発音は「ビアズリ」。ついつい、やってしまう。 |
|