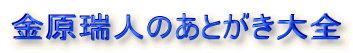
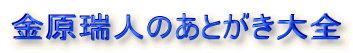
|
二ヶ月のごぶさたでした(というふうに書くと、玉置宏みたいだな……なんてジョークは、もう若い連中にはわからない) 1. もう明日はアメリカなので、頭がもうろうとしているところなのだが、62回続いてきたこの「あとがき大全」を今回もパスするというのは、いやなので、簡単な解説と、あとがきだけ。 2. まずラドヤード・キプリングの『プークが丘の妖精パック』が出たんだけど、このあとがきと解説はかなり長いので、ここでは省略。気になる人は本屋で立ち読みしてください。光文社古典新訳文庫です。 というわけで、ここに載せるのは『ツォツィ』『魔使いの弟子』『グッド・オーメンズ』の三作品のあとがき。ただし、これは原稿のままなので、まだ手直しのまま。本のあとがきとはちょっと違うところがあります。 3.あとがき(『ツォツィ』『魔使いの弟子』『グッド・オーメンズ』) 訳者あとがき(『ツォツィ』) 満員電車のなかで、四人の少年が大柄な男をかこむ。そのうちのひとりが、男の背後から自転車のスポークで心臓を貫く。三人が体を押しつけるようにして男を支えているあいだに、ひとりがポケットから給料袋を抜き取る。 その金を持って酒場にくりだした少年たちは、やがてけんかを始める。 舞台は南アフリカの黒人居住区”タウンシップ″。極度に貧しい地域で、トタン板を組み合わせて作ったような家が密集し、地域でひとつだけの水道の前には連日、バケツを持った人々の行列ができる。主人公は不良グループを仕切っている「ツォツィ」と呼ばれる少年。ツォツィというのは、不良やギャングを意味する言葉で、本名ではない。彼は自分の名前と過去を心の片隅に封じこめ、売春や不法の酒場がはびこるスラム街で、暴力と略奪の日々を過ごしている。 自分の内側をのぞくと、闇が見えた。それは、真夜中の闇に似ているが、それよりもっと暗い。夜、ベッドに横たわっていると、闇がつながっていくのを感じた。内と外の闇を自分の肉体が隔てている。やがて、眠りがおとずれ、それがひとつに合わさってしまえば、あとはもう黒一色の世界だ。夢は一度も見なかった。 もちろん希望はない。しかし、希望のないところには絶望もない。 そんなツォツィがある日、奇跡を手にするところから、この物語は動き出す。襲おうとした女に押しつけられ、思わず受け取ってしまった靴箱の中のしわくちゃの赤ん坊が、いきなり彼の闇のなかに割りこんできたのだ。 ツォツィは赤ん坊を持てあまし、いらだたしく思いながらも、死なせてはならないと感じるようになっていく。しかし、赤ん坊は彼が固く封じこめてきた過去の扉をこじ開けてしまう。やがて、希望とともに絶望がよみがえり、ツォツィは自分自身と向かい合うことになる。 ある疑問が弾丸のようにツォツィの頭をぶち抜いた。おれはいつそんな選択をしたんだ? 怒りと興奮がごちゃまぜになり、ツォツィは身震いした。立ち上がって、あたりをきょろきょろ見回す。おれはそもそも、いつ、どうやって、そんな選択をしたんだ? 現在と過去、光と闇の間をめまぐるしく行き来しながら、かすかに見えてきた未来に向かって歩み始めたツォツィはいったどこにたどりつくのか……。 いま思い返すと、この作品を訳しているときはずっと、自転車のスポークの先を背中に突きつけられているような感じがしていた。最初の殺人から強烈なラストシーンまで、異様な緊張感がみなぎっていて、気の抜けるところがなかった。そしてなにより、この疾走感。いきなりすさまじい勢いで走りだした車が、どこまでも加速しつつ、消滅点---ヴァニッシング・ポイント---に突っこんでいくような爽快感がある。 訳し終えてふと、世界にはすごい作品があるものだなと思った。おそらくいまの日本人には絶対に書けない種類の小説だろう。傷口に塩を塗りこまれるような痛みが全編を走っているが、信じられないほど切なく迫ってくる魅力がある。 少しだけ解説を。作者はアソル・フガード。一九三二年、南アフリカ生まれの劇作家で、母親はアフリカーナー、父親はイギリス人。若いときから反アパルトヘイト運動に参加し、白人でありながら黒人と共に戯曲を上演するなどして政府から目をつけられ、パスポートを没収されたこともある。演劇のさかんな南アフリカでは、誰もが知っている”超″が付くほどの有名作家。 作品が書かれた当時の南アフリカではアパルトヘイトと呼ばれる「人種隔離政策」がとられていて、少数の白人が政治経済の実権を握り、大多数の黒人は徹底的に搾取され、貧困にあえいでいた。(一九九一年になって、ようやく廃止され、一九九四年には初の民主主義選挙で黒人大統領、ネルソン・マンデラが選出された) 物語の舞台になっているタウンシップもこうしたアパルトヘイト政策から生まれた街。やせた土地に押しこめられて生活できず、ガンブートのように出稼ぎを余儀なくされた黒人たちが住んだ。都市周辺でも黒人は一定地域にしか住むことができなかったから、そこから白人地区に働きに出て、夜戻ったのだ。ボストンたちが偽造したパスもまた、政府が黒人たちをがんじがらめにする手段のひとつだった。 仕事も得られず、家族とも一緒に住めなかった者が多いタウンシップには、当然のように犯罪がはびこる。同じ黒人を襲って盗みや殺人、レイプをする若いギャングたちがツォツィと呼ばれた。自転車のスポークで心臓をひと突き、という殺しの手段は実際に使われており、外科医も驚くほどの正確さだったとか。ツォツィたちは恐れられる存在だった。 フガードがツォツィを主人公にした小説を書き始めたのは一九六〇年。一九六一年には、フガードの戯曲『血の絆』が南アフリカで上演された。ロンドンから来ていた出版社の人がこの芝居を観て感動し、彼に小説はないのかとたずねたらしい。そのためフガードは一旦中止していた『ツォツィ』の執筆を再開した。が、気に入らず「やっぱり自分は劇作家だ」と思って出版を断念する。書いた本人はその存在を忘れ去っていたが、原稿は破棄されないまま残っていた。七〇年代の半ばそれが他の原稿と一緒に荷造りされて国立英国文学博物館のフガード作品保管庫に送られ、何人かの目にとまる。編集をして出版をすべきだと勧められ、フガードはよく考えた末にそれを受け入れた。約二〇%を削る形で編集された原稿を、ほぼ二〇年ぶりに読み直し、出版を承認。一九八〇年、南アフリカ、アメリカ、イギリスで出版のはこびとなり、絶賛される。 その後この物語に魅了された人々により何度か映画化が試みられ、数本の脚本が書かれた。が、主に主人公の心の変化を描いた作品だったため、映像化は難しい。プロデューサーのピーター・フダコウスキ、監督・脚本を手がけたギャヴィン・フッドによってようやく映画化に成功したのが二〇〇五年。出版からさらに二十年以上の時がたっていた。映画は各国の映画祭で評判になり、二〇〇六年アカデミー賞外国語映画賞を受賞した。 最後になりましたが、この本に訳者以上に関わってくださった編集者の吉田好見さん、原文とのつきあわせをしてくださった鈴木由美さん、細かい質問にていねいに答えてくださった作者のアソル・フガードさんに心からの感謝を! 二〇〇七年二月二十八日 金原瑞人 訳者あとがき(『魔使いの弟子』) 古今東西、魔法を使う者がいれば、魔法を封じる者がいる。そして、ヴァンパイアがいれば、ヴァンパイア・ハンターがいるし、魔物がいれば、魔物を封じる者がいる。RPGでも「魔封じ」の術があるし、日本でも昔から弘法大師や上人様や阿弥陀様に封じられた魔物は数知れない。中国でも『西遊記』を読めば、孫悟空をはじめ、お釈迦様に封じられた魔物も決して少なくないことがよくわかる。 古今東西、悪しき魔物がいれば、善き「魔の封じ手」がいた。しかし一般には、魔物が魔法を使い、呪文を使えば、「魔の封じ手」は同じように、魔法を使い、呪文を使ってそれと戦う。魔法対魔法、妖術対妖術、呪文対呪文の戦いになる。つまり、化けくらべ、魔法くらべ、力くらべになっていく。 ところが、この『魔使いの弟子』はたまにある例外で、そこがおもしろい。「魔使い」というのは「魔法使い」とは違って、魔法は使わず、自分の感覚を頼りに悪を封じる職人で、主な仕事は、悪しき魔女や霊の力を抑え、できれば封じこめること。しかし使うのは、自分の経験から収集した相手の情報や、代々の魔使いがつけてきた記録、そして鉄、塩、銀の鎖、杖などで、特別な魔法も武器もない。 いってみればこの作品は、超自然な力を持つ悪しき者を相手に、ごく普通の(ちょっと感覚の鋭い)人間が、それまでに蓄積されてきた知識と独特の勘を武器に戦う物語といってもいい。 主人公は十二歳の少年トム。トムは魔物が大嫌いだし、どうしても弟子入りしたいわけではないけれど、大好きな母さんをがっかりさせたくないし、ほかに就けそうな職がないという、ちょっと情けない理由で魔使いの弟子入りをすることになる。ただ、トムは「七人兄弟の末っ子である父さん」の「七番目の息子」であり、「七番目の息子の七番目の息子」だけが持つ特別な能力を備えているらしい。だから生まれながらにして、この仕事につくよう運命づけられているのかもしれない……のだが怖いものは怖いし、自分が本当に「魔使い」になれるかどうかもはっきりとはわからない。とりあえず、弟子になってみる、という感じでこの物語は幕を開ける。 その他の主要な登場人物はまず、師匠。師匠はフードつきの黒いマントをすっぽりかぶった、孤独でわけありの魔使い。見るからに恐ろしげで、謎めいていて、取っつきにくい。それからもうひとり、「黒いワンピースにとんがった靴」のかわいい女の子アリス。このアリス、じつは敵か味方かよくわからない不思議な存在だ。とても魅力的な女の子なのだが、トムはアリスを友達のように近く感じたり、裏切りのうまい敵のように感じたりする。アリス自身も自分のことがよくわかっていないのかもしれない。 主人公のトムはまっすぐで責任感があるが、弱くもあり頼りなくもあるし、魔使いは自分の仕事に対して確固たる信念をもちながらも、トムも知らない何か暗い過去を抱えている様子だし、アリスは善と悪の間を行ったり来たりしている。中心にいる三人が三人とも不完全で揺れているところがまた、この作品の大きな魅力になっている。 そして、忘れてならないのがトムと師匠の敵役、魔女マザー・マルキン。おそらくこの作品で最もユニークで、異様な存在感を放っているのはこの魔女かもしれない。その恐ろしさ、不気味さは、この本のいちばんの売りだと思う。 また、作品にランカシャーの実在の地名や伝説の不思議なものたちが出てくるのも楽しい。 ランカシャーは作者が長年暮らしてきた土地で、精霊ボガートなどの伝説が数多く残っている。作者は教員時代、地元の民話を生徒たちにたくさん読み聞かせてきた経験もあり、この地に大いに触発されたらしい。地名や伝説を独自の感覚でひとひねりして、物語にさりげなく盛りこんでいる。たとえば、扉に出てくるウォードストーンは、ランカシャー北東部にある荒涼とした丘のてっぺんにウォー★ズ【★傍点】ストーンという名で実在する。本書に何度か出てくるペンドルも、ランカシャーに実際にある、魔女裁判で有名な場所だ。毛むくじゃらのボガートや★玄関荒らし【★ルビ ホールノッカー】などは、伝説からとって創作を加えたという。 少しだけ作者の紹介をしておこう。 ジョゼフ・ディレーニーは一九四五年、イギリスのランカシャーで生まれた。プレストン・カソリック・カレッジに入学するが、やめて十六歳で整備工見習いに。働きながら、夜学に通うようになり、ランカシャー大学に入る。卒業後、セント・マーティンズ・カレッジで学び、教師になる。ブラックプール・シックスス・フォーム・カレッジでは、映像・メディアの学部で主任を務めていた。のちに、コンピューターのプログラマーを目指して勉強を始め、そのときタイピングの訓練になるからと小説を書いたのがきかっけで、以来、創作の道へ。しばらく大人向けの小説を手掛けていたが、エージェントからのアドバイスで児童書を書いてみたところ、これがヒット。その作品が本書で、現在、日本を含めて十五か国で翻訳出版されている。 今作者が住んでいるストーマイン村(本書で「ストーミン村」の名で登場させている)には、ホールノッカーが司祭によって教会の小屋の下に拘束されているという伝説が残っているそうで、作者はこう言っている。「わたしはボガートのテリトリーのど真ん中に住んでいるんです」 なお、本書はシリーズもので、現在イギリスでは三巻まで出ている。第二巻『魔使いの呪い(仮題)』では舞台を大聖堂の地下に広がる巨大なカタコンベ(地下墓地)に移し、さらにスケールの大きな、すさまじい戦いが繰り広げられる。 最後になりましたが、編集の小林甘奈さん、原文とのつきあわせをしてくださった秋川久美子さん、すてきな挿絵をつけてくださった佐竹美保さん、質問に快く答えてくださった作者ジョゼフ・ディレーニーさんに心からの感謝を。 二〇〇七年二月二日 金原瑞人・田中亜希子 訳者あとがき 『コララインとボタンの魔女』『アナンシの血脈』、そしてこのプラチェットと共作『グッド・オーメンズ』。まったく、よくもこんな本を書くもんだと思う。 「こんな本」とはどんな本かというと説明に困るが、人を食った話……というか、奇想天外な話……というか、だれも思いつきそうにない話……というか、ぶっ飛んでる話……というか、ファンタジーとも幻想文学ともつかない話……というか、なんとなく深い意味がありそうに思えるけど、実際はただの冗談かもしれないんだけど、もしかしたらと思わせるような話……というか、歴史から文学から神話からサブカルから単なる雑学まで異様によく知っている天才のお遊びのような格好をした爆弾みたいな物語……というか、『神曲』と『ドン・キホーテ』と、『惑星ソラリス』と『ロッキー・ホラー・ショー』と、『もののけ姫』と『エヴァンゲリオン』と、松岡正剛とビート・たけしと、草間弥生と奈良美智と、吉本隆明と吉本ばななと、手塚治虫と古屋兎丸と、蜷川幸雄とペンギンプルペイルパイルズと、そんなものを全部まとめてごっちゃにしたような物語……というか、……これを続けているときりがないからこのへんでやめておくけど、ある意味、ごった煮、しかしある意味、神話的混沌と、現代という混沌と、人間と神と天使と悪魔という混沌が織りなす、前代未聞の壮大な絵物語といってもいいかもしれない(もちろん、混沌的なばかばかしさやくだらなさもふくめて)。 具体的にどんな話かというと……ハルマゲドンの種子としてひとりの赤んぼうが生まれ、その子の成長とともに世界滅亡の日が近づいてくる、というふうな話。 ただ、その赤んぼうは生まれたときに取り違え事件があって、しかるべき親のもとで育たず、そもそもアダムというおめでたい名前をつけられ、お供にと送られた地獄の番犬も、その影響のもとで小型犬になってしまい、猫とけんかをしては負け続ける(けど、この犬、地獄で人間を追いかけても逃げるばかりでつまらなかったので、こんな状況を楽しんでいたりする)。また一方、神様の手先と悪魔の手先が手を結ぶことになる(このふたりが主人公だったりして)。長年敵同士であれこれやってくるうちに、気心も知れたふたりは、この世界が滅亡したら、つまんないもん、というところで意見が一致、ハルマゲドンを阻止しようと奮闘する。 まあ、いってみればスラプスティック(どたばた風)ハルマゲドン・ストーリーだが、あちこちに驚くようなイメージの地雷が仕掛けられている。とくに黙示録に出てくる馬に乗った四人なんか、いい味を出している。そして四人に向かい合う、登場人物のひとりビッグ・テッドもさらにいい味を出している。 しかし、ビッグ・テッドのどうしようもない無知が、彼の楯となり鎧となった。ビッグ・テッドは動かなかった。 「ふん。ヘルズ・エンジェルズね」ビッグ・テッドはいった。 〈戦争〉がビッグ・テッドに向かって、だらしない敬礼をしてみせた。 「そうよ、ビッグ・テッド。わたしたちは正真正銘の本物なの」 〈飢餓〉がうなずいた。「古くからの一派だ」 〈汚染〉はヘルメットを取って、長く白い髪をひるがえした。彼は〈疫病〉がペニシリンについてぶつぶつ文句をいいながら一九三六年に引退したときに、そのあとを継いだ。将来どんな可能性があるか知っていれば、〈疫病〉だって引退などしなかっただろうが……。 「ぼくらは口先だけじゃなくて、ほんとうに約束を果たす」〈汚染〉がいった。 ビッグ・テッドは四人目の騎士をみていった。「おれはあんたを前にみたことある。ブルー・オイスター・カルト(アメリカのロック・グループ)のアルバムジャケットにのってただろ。おれはあんたの……あんたの頭がついた指輪ももってる」 〈わたしはどこにでもいる〉 にやっと笑うのもよし、深い意味をくみとるもよし、聖書を読み直すのもよし、ロープシンの『蒼ざめた馬』を読むもよし、古川日出男の『アラビアの夜の種族』を読むもよし、ゲイマンの「サンドマン」を読むもよし、また『千夜一夜物語』を読むのもいいだろう。 とにかく、まあ、こんな本だ。 物語の世界に逃げこみたい人にとって、これほどいい本はないと思う。 さて、『コララインとボタンの魔女』『アナンシの血脈』『グッド・オーメンズ』と続いてきたが、じつは、超弩級大型娯楽思索幻想SFファンタジー、American Gods が次に控えている。こうご期待、なのだ。 なお、最後になりましたが、編集の津々見潤子さんに心からの感謝を! 二〇〇七年一月二十六日 金原瑞人 訳者あとがき(『エリオン国物語 III) 「エリオン国物語」、ついに最終巻。 秘密の扉の鍵を手に入れたことからはじまったアレクサの冒険の最後を飾るのは、創造主エリオンと堕天使アバドンのすさまじい戦いだ。 第二巻『ダークタワーの戦い』で、アレクサと仲間たちは、アバドンの手先グリンドールを破滅寸前まで追いつめながら、あと一歩というところで逃したうえに、ヤイプスも人質に取られてしまった。ヤイプスを取りもどすには、最後の魔法の石を持ってグリンドールが待つブライドウェルに、五日以内にたどり着かなければならない。 また旅がはじまる。それも今度は、これまで以上に苦しい旅で、海で大波にのまれたり、切り立った断崖で宙づりになったり、魔法の石まであやうくなったり……思いも寄らない危機が次々にアレクサたちを襲う……が、思いも寄らない出会いや再会も待っている……そしてその先に、最後の最後に待ちかまえているものは……! 二巻目まで読んできて、この三巻の終わりまで読み終えた読者は、アレクサと同じような、いや、アレクサ以上の感動を味わうことだろう。そしてまた、一巻目から読み返したくなるはずだ。 振り返ってみれば、この三巻にわたる物語は、アレクサにとっては発見の旅でもあった。町の外の世界に足を踏み出して以来、アレクサは自分を取り巻く人々や世界のほんとうの姿を次々に目の当たりにしてきた。第一巻では、犬猿の仲だったパーヴィスの意外な素顔とずっと信頼してきたガネーシュの正体を知り、第二巻では、ウォーヴォルド夫妻の過去とエリオン国の秘密と危機を知った。そして、この第三巻では、自分についての大きな秘密を知り、「目に見えるものが真実とはかぎらない」ことを知る。 冒険、冒険、また冒険の、このファンタジーは、旅と発見と成長の物語でもあった。 エリオン国物語三部作で作家デビューしたパトリック・カーマンさんは、現在、SFファンタジーの三部作を執筆中で、その第一巻がこの四月にアメリカで刊行されるらしい。そして、うれしいことにエリオン国物語の新シリーズの刊行もすでに決まっているという。その第一弾は、ウォーヴォルドとローランドの少年時代の冒険物語! ひょっとすると、アレクサやヤイプスとまた一緒にハラハラドキドキできる日も来るかもしれない。 なお最後になりましたが、編集の野田理絵さん、原書とのつきあわせをしてくださった西本かおるさん、そしてなにより、細かい質問にていねいに答えてくださった、作者のパトリック・カーマンさんに心からの感謝を! 二〇〇七年二月十二日 金原瑞人・小田原智美 |
|