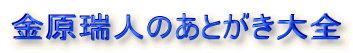
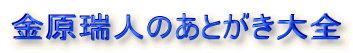
|
1.暇について この頃、時間って、しぼればしぼっただけ取れるんじゃないかという気がする。つまり、11時から13時まで打ち合わせがあって、そのあと14時から次の用事があるとして、その日にどうしてもという用事ができた場合、11時からの打ち合わせを30分早めてもらって、14時からの用事を30分遅くしてもらえば、なんとかその間に入れられたりするのだ。 手の上にパチンコ玉をのせられるだけのせても、あとひとつならのせられる。ということは、もうひとつはのせられる。ということは……と繰り返せば、無数にのせることができる……という錯覚に陥ることがよくある。 もちろん、それはまだまだ余裕があるからしぼれば出てくるというだけのことで、逆にいえば、まだ時間に余裕があるということだ。 しかしこれを続けていくと、「余裕」がなくなる。そして思わぬエラーが多くなる。なにより、細かい対応、細かい気遣いができなくなってしまう。お礼の手紙やメールがついつい短くなる、おろそかになる。そのうち、うっかり出し忘れてしまったりする。 そしてそして、なによりなにより、「あとがき大全」が短く短くなっていく。 いかんなあと思う今日この頃なのだった。 2.あとがき:『武器よさらば』(光文社古典新訳文庫)『スターダスト』(角川文庫)『魔使いの呪い』(東京創元社)『ミッドナイターズ2』(東京書籍)訳 そうそう、「やまねこ翻訳クラブ」の作ってくださっている訳書リストによれば、『ミッドナイターズ2』が298冊目の訳書らしい。300冊目はいったい、なんになるんだろう。 訳者あとがき(『武器よさらば』) ヘミングウェイって、なんで、こんなに魅力的なんだろう。なんでこんなにおもしろいんだろう。不思議でしょうがない。二十世紀のアメリカ作家のうちひとりだけ選べといわれたら、文句なくヘミングウェイだと思う。 ちょっと、アメリカ人でノーベル文学賞をもらった人をあげてみようか。 シンクレア・ルイス、ユージン・オニール、パール・バック、ウィリアム・フォークナー、アーネスト・ヘミングウェイ、ジョン・スタインベック、ソール・ベロー、アイザック・バシェヴィス・シンガー、チェスワフ・ミウォシュ、トニ・モリスン。 ルイスが一九三〇年、モリスンが一九九三年の受賞、というわけで全員が二十世紀の作家といっていいんだけど、このなかでヘミングウェイ以上に目立つ存在がいるだろうか。 もちろんノーベル賞受賞作家以外にも、戦後のアメリカには、D・J・サリンジャー、カート・ヴォネガット、フィリップ・ロス、ジョン・アップダイク、ドナルド・バーセルミ、トマス・ピンチョン、ジョン・アーヴィング、ポール・オースターなど、数えきれないくらいのおもしろい作家が続々と登場してきた。 が、個人的な好みはさておき、ヘミングウェイを超えるくらい存在感のある作家がアメリカにいたかとなると、自信を持って「イエス」と答えることのできる人は少ないと思う。 ある編集者から、「いま、だれかの全集の個人訳を出すとしたら、だれを選びます?」とたずねられたことがあった。それまで考えたこともなかったけど、即座に、「シェイクスピアとヘミングウェイ」という答えが口をついてでた。 シェイクスピアは、その作品すべてが好きなわけではないけど(代表作の『ハムレット』とか、どこがいいんだろうと思ってしまう)、どの作品も思いきり遊べて楽しそうだ。それに対して、ヘミングウェイの作品は翻訳自体ではあまり遊べそうにないけど、なぜか読んでいてとても快い。そして訳していてとても快い。なにがそんなにとても快いんだときかれると、ちょっと困るが、つきつめて考えてみると、あの切なく、感傷的なところじゃないかと思う。それがすっと胸に入ってくる。ヘミングウェイって、案外とセンチメンタルなのだ。 ヘミングウェイというと、ずいぶんマッチョなイメージが強い。ボクシング、闘牛、釣り、ハンティング……高校ではフットボールや水泳や陸上なんかもやっていたらしい。それに、自ら戦争に飛びこんでいった。また、キーウェストやキューバでの豪快なトローリングや、アフリカでの勇壮なライオン狩り。こういったイメージにさらに輪をかけているのが無類の酒好き……というよりアル中だったという事実だろうか。ただ、当時のアメリカの作家はアル中が多かった。ヘミングウェイのほかにも、オニール、フォークナー、フィッツジェラルドなど、みんなアルコール依存症といっていい。 そういう経歴や好みをながめると、男性的で、いかにもアメリカ的な感じがするんだけど、作品を読む限りでは、とても女性的で、繊細で、ヨーロッパ的で、センチメンタルな気がしてならない。 『武器よさらば』は最初の長編小説で、ヘミングウェイはこれで一躍、流行作家のひとりになる。 舞台は第一次世界大戦中のイタリア戦線。主人公は、二十代半ばのアメリカ人、フレデリック・ヘンリー。傷兵を運ぶトラック数台を指揮している中尉だ。ヘンリーは、イギリスからやってきた看護婦のキャサリンと出会い、やがて戦場で重傷を負い、ミラノの病院でキャサリンと再会し、おたがい愛し合い、そして脱走……という展開そのものがセンチメタルだ。 この作品、後半からいきなり厭戦的になり、その一方で、みずみずしい恋愛物語が進行していく。この虚無感とロマンチックな躍動感、そして……という、いかにもありきたりな展開が、ヘミングウェイの手にかかると、がぜん、鮮やかに生き生きと迫ってくる。 そして、エンディングもセンチメンタルで印象的で映像的だ。とくに、「雨が降っていた」というさりげない最後の一文は、ぞくっとするほどのインパクトがある。 おそらくこのあたりが、ヘミングウェイは通俗的だと批判される理由のひとつなのだろう。しかしそれこそ、ヘミングウェイの魅力でもあり、そこにこそ時代を超えて読みつがれるおもしろさがあるのだと思う。そもそも、ヘミングウェイが通俗的だというなら、スタンダールやユゴーはもっと通俗的だ。 センチメンタルという言葉は、センチメントという言葉から派生していて、センチメントというのはもともと「人間的な気持、感情」という意味だ。その根源的な意味において、ヘミングウェイはセンチメンタルなんだと思う。 おそらく、最初にあげた十数名のアメリカ現代作家のうち、ヘミングウェイほど人の心をうつ作品を多く書いた人はいないと思う。人間の深い部分に触れてくるからだろう。 ともあれ、『武器よさらば』は文学的であろうが通俗的であろうが、文句なくおもしろい。どうか、気軽に楽しんでください。 なお最後になりましたが、ていねいに原稿をチェックしてくださった編集の堀内健史さん、原文とのつきあわせをしてくださった野沢佳織さん、イタリア語のチェックをしてくださった高橋隆子さん、原文に関する疑問にひとつひとつ答えてくださったカレン・滝沢さんに、心からの感謝を! 二〇〇七年六月 金原瑞人 訳者あとがき(『スターダスト』) ニール・ゲイマンの一般向けの作品は、なかなか一筋縄ではいかない。たとえば『グッド・オーメンズ』『アナンシの血脈』『アメリカン・ゴッズ』(そのうち翻訳が出る予定)なんかはすべて、ひとひねりもふたひねりもしてあって、そのうえストーリーはおもしろくおかしく脱線するし、ときどき思わぬ知識や情報が虚実を問わず飛びかうし、あちこちに伏線がらみのアトラクションが仕掛けてある。本筋と脇筋を軽妙にアクロバチックに行き来しながら、全体をユーモラスに、ウィッティに、アイロニカルに彩りながら、最後は見事に収束する。いかにも現代的なストーリーテラー、ニール・ゲイマンは、容赦なく読者の想像力を試してくれる。 ところが一九九九年に出版された『スターダスト』はいささか風合いが違う。ほかの作品よりちょっと初々しく、ちょっとストレートで、ちょっとほほえましく、ちょっとはにかみがちで、思いきりロマンチックなのだ。 時はヴィクトリア朝、トリストランというイングランドの青年が、心を寄せた女の子のために「流れ星をさがしにいく」という冒険物語だ。そして冒険の舞台は妖精の世界。一方、何千年も生きてきた魔女が若さを取りもどすために、その流れ星の化身である少女を追い、またある国の残酷非情な王子たちが玉座を手に入れるために、その少女を追う。さらにその争奪戦に参入するもうひとりの魔女と、その魔女に捕らわれている小鳥。 冒険、剣、魔法、妖精、追跡、逃亡……まさに王道中の王道をゆく、本格ファンタジーなのだ……が、ゲイマンの手にかかると、なぜかかすかに王道をはずれて、大人好みにおもしろくなってしまう。困ったものだ。もちろんヤングアダルトから十分に楽しめる、いや、夢中になれるファンタジーなんだけど、とことん楽しみつくせるのは、人生にちょっと疲れた大人なのかもしれない。 『ハリー・ポッター』は子ども向けだけど、大人も楽しめる。『スターダスト』は大人向けだけど、子どもも楽しめる。似ているようだけど、この違いは大きい! エンディングも、王道ファンタジーらしく堂々としめくくられるものの、そこはかとなく切ない。なんとなく『アーサー王物語』や『指輪物語』を思い出させる。 さて、ゲイマン度の高さの順に四作品を並べると、『アメリカン・ゴッズ』>『グッド・オーメンズ』>『アナンシの血脈』>『スターダスト』という感じ……なので、この『スターダスト』、百%ゲイマン・ファンにはちょっと物足りないかもしれない……が、垣根を越えたおもしろさという点では満足度百二十%。ゲイマン好きもゲイマン嫌いも、ファンタジーと冒険が好きなら(あるいは楽しい現代小説が好きなら)、まずは読んで損はない。 蛇足ながら、映画もおもしろい。後半は原作とかなり違うが、映画ならではの工夫があちこちにこらしてあって、原作を読んでからでも楽しめるし、笑える。 それからひとつお断りを。じつはこの作品の登場人物はほとんどみんな、'boots' を履いている。これを一々「ブーツ」とか「長靴」と訳すと目障りなので、一括して「靴」と訳しておいた。 最後になりましたが、編集の津々見潤子さん、原文とのつきあわせをしてくださった松山美保さん、質問にていねいに答えてくださったニール・ゲイマンさんに心からの感謝を! 二〇〇七年八月十五日 金原瑞人 訳者あとがき(『ミッドナイターズ2』) 発想もイメージもストーリーも、いままでのファンタジーとはちょっとちがう、そして雰囲気はまるっきりちがう、新感覚ファンタジーの第二巻『ダークリングの謎』(Touching Darkness)。 このシリーズは、前巻のあとがきでも書いたとおり、大人っぽくてシャープで、危うくて危ないファンタジーなんだけど、今回、その「クール度」が急激にレベルアップ。 場所はアメリカ中西部オクラホマ州のド田舎ビクスビー。ここでは深夜十二時からの一時間が「ブルータイム」だ。世界が青く染まり、大きな黒い月が輝き、だれもが凍りついたように動かなくなってしまう。動けるのは「ダークリング」と呼ばれる、残酷で不気味なモンスターたち。そして、若者たち五人。彼らは「ミッドナイター」と呼ばれている。 この五人が物語の中心だ。ブルータイムの間だけ重力から解放されて自由に宙を飛ぶことのできるジョナサン、いつも他人の感情や気持ちがいやおうなく頭に流れこんでくるメリッサ、ブルータイムやブルータイムの歴史や、この時間帯に現れるモンスター、「ダークリング」に詳しいレックス、数字と数学のことを異様によく知っていて、ダークリングよけの金属の武器を作るのが得意なデス。そして、新たにこれに加わった転校生ジェシカは、ブルータイムの世界でただひとり、「火」を自在に操ることができる。 その五人がそろって、まずダークリングと戦うことになったのが、第一巻だった。 そして第二巻は、ダークリングたちがいきなり凶暴さを増し、人間まで仲間に加えて、前回をはるかにしのぐ壮絶な戦いを挑んでくる。そのうえダークリングは五人を抹殺しようとしているだけではなく、さらなるおぞましい計画を実行に移そうとしていたのだ。 ところが、ダークリングの攻撃を受けて立つ五人は、それぞれ個性があまりに強く、おたがいに反発し合い、いまにもばらばらになってしまいそうだ。 ブルータイムだけでなく、残りの二十四時間も戦わなくてはならなくなった五人はダークリングの必死の挑戦をはねのけて、生きのびることができるのか。そしてまた、新たに判明したいくつもの新事実は五人をどこに導いていくのか。 そして最終刊、つまり次の第三巻では、さらに思いがけない事実が明らかになる。どうか期待して待っていてほしい。 なお、最後になりましたが、大活躍のリテラルリンクのみなさん、原文との中田香さんに心からの感謝を! 二〇〇七年八月十五日 金原瑞人 |
|