「子どものための文学」と書きましたけれど、それには大人が望む子ども像は何かを、子どもに伝える道具としての機能も含まれているでしょう。児童書を読むことで、子どもはその子ども像を学習し、自らをそれに当てはめていく。
子どもの楽しみの道具であると同時に、大人の意図を学習するそれ。児童書は時にそうした二重性を持って存在します。
例えば、児童書の古典の一つ『若草物語』(1868)はその良い例を私たちに示してくれるでしょう。
父親のマーチ氏は、従軍牧師として南北戦争に出征していて不在のマーチ家は、母親のマーチ夫人と、メグ、ジョー、ベス、エイミーの四姉妹が暮らしています。物語はクリスマスの前日、父親から来た手紙を母親が読むことから始まります。手紙は四姉妹に、留守の間、母親の言い付けを良く守って、父親が帰った時には、小さなご婦人(原題の「 Littel Women」)になっていることを望むとあります。四姉妹は、この要請に従うと母親に誓う。ところが、小さなご婦人であるには問題な点が、それぞれにあります。メグはお金持ちの生活に憧れているし、ジョーは男勝りで乱暴だし、ベスは内気すぎて人前に出ることができない(そのため彼女は学校にも行っていません)し、エイミーは自分本位でわがままです。ですから誓ったはいいが、どうしてこのような悪い部分を直し、克服していくか? それがこの物語のエピソードを作っていくわけです。
長女のメグを例に挙げれば、彼女はパーティーに行くときおしゃれをしようと、焼きゴテで髪をカールすることをジョーに頼むのですが、粗忽なジョーに、髪の毛を焼かれてしまう。出かけたら出かけたで、ダンスを踊りすぎ、足首を捻挫する。果ては、家が貧乏だから、お金持ちのお隣、ローレンス家の跡取ローリーを狙っているという、屈辱的な噂まで巻かれてしまいます。そうして彼女は虚飾の悪に気づき、貧乏だけど、愛情と誠意に溢れたローリーの元家庭教師のブルック氏と結ばれ、幸せになる。つまり、まず罰があたえられ、反省し、良き婦人となっていくことの褒美として幸せが訪れるわけです。
この一九世紀半ばに書かれ、ベストセラーとなった物語が、子ども(女の子)読者に伝える、「小さなご婦人」になることが女の子にとって幸せなのだとのメッセージは、現代の私たちの目から見ると、かなり問題含みでしょう。つましく、清楚で、おとなしく、父親や夫に従う女が求められているのですから。ちなみに、「Littel Woemen」の続編のタイトルは「Good Wives」(『良妻』)です。
しかし、だからといって、この物語が、女性像の古臭い価値観を読者に押し付けるものだと、簡単に片付けるわけにはいきません。なぜならそれは今でも子ども読者に喜びを持って読み継がれているのですから。
その理由は、今ご紹介したような、(当時の)親が望む子ども像(女の子像)を読者に示しながら、同時に、当時から現代までの女の子が憧れる女の子像もここには描かれているからです。すなわち、小さなご婦人からはもっとも遠いキャラクターのジョー。もちろん彼女も最終的にはご婦人になっていくわけですが、そうなることを条件にして(つまり、社会に受け入れられる物語に仕立てて)、目いっぱいそこから外れた女の子像を、当時としては物語の中では描かれることのなかったそれを、描いてみせたのです。
男勝りで、頭が良く、走ることも平気で、自立心が強く、将来は作家となって一家を養う野望を持つ女の子。それがジョーです。
当時の女の子は、そこに全く新しい女の子の生き方を見出したのでしょうし、現代の多くの女の子はジョーに共感しているわけです。物語が、いくらそれが小さなご婦人として、いけない像なのだと主張しても、彼女たちはジョーを支持する。
『若草物語』はそうした二重性を持っているのです。
ですから、現代の大人である私たちにとってこの物語は、次のようなことを教えてくれます。まず、一世紀半ほど前のアメリカで大人は、どんな女の子像を望んでいたか。一方、女の子読者はどんな女の子に憧れていたか。そして、今もジョーが支持されているとしたらそれは、ジョー的な女の子像が今でも完全に社会に受け入れられてはいないのであろうこと。
*
優れた児童書の多くは子どもたちが生きている時代の価値観や状況を、それを肯定的にしろ否定的にしろ子ども読者にわかる形で伝えようとし、と同時に子どもたち自身の願望や感性をできるだけリアルにつかみ取ろうとしています。児童書の作家は大人であるにもかかわらず、子どもの側から世界を観ようとするのです(それが先ほどの二重性を産んだりするわけです)。
大人がわざわざ児童書を読む楽しみの一つはそこにあります。あくまで作家が想像した範囲とはいえ、私たちの世界が子どもにどう映っているのかをかいま見ることができますし、私たちは彼らとどう向き合えばいいのかを考えさせてくれます。
さて現代の児童書はどういう子どもの風景を提示しているのでしょうか?
例えば、離婚を題材にした物語を見てみましょう。これは七〇年代まで、児童書では殆ど扱われませんでした。両親にそんな事態が起こる可能性を、わざわざ子どもに伝える必要はないというわけです。ところが、欧米では離婚率の増加とともに、現実的に無視できなくなり、そうした物語が徐々にでてきます。日本でも九十年以降、増えていますが、ここ数年の描かれ方は、「子どもというモンは、おとなの現実をうけいれ」なければならない、「子どもはひとりでは生きていけんさかいナ」(『はじまりは・ごっこ・から』高科正伸 岩崎書店)だとか、「かけがえのない父親であり、母親であっても、父と母は他人なのだ。いやになったり、うまくいかなかったら、別れるしかない」「子どもの朝子には、どうにもできないことなのだ」(『12歳、いま/ガラスの季節』津島節子 ぶんけい)と、現実をかなりあからさまに提示するものとなってきています。
 これはなにも日本の児童書に限らず、ドイツの物語『屋根にのるレーナ』(ペーター・ヘルトリング 上田真而子訳 偕成社)では、養育権裁判で主人公は、「パムとマムはぼくたちが生まれてくるのをねがっていました。なんべんもそういってました。ぼくたちはパムとマムがのぞんだ子どもです。すくなくとも、まえはそうでした。いまはもうちがいますけど」と言い放ちます。またスェーデンの、『夜行バスにのって』(ウルフ・スタルク
遠藤美紀訳 偕成社)に至っては、「かあさんが家を出て再婚してしまってから、父さんにはシクステンしかいませんでした。だけど、だれかの、たった一つのものでいることは、そんなにかんたんなことではありません」と考える主人公は、このままではいけないと、父さんに新しい伴侶を見つけようと画策を始めるのです。アメリカの『がんばれセリーヌ』(ブロック・コール 戸谷陽子訳 徳間書店)は、父親が再婚した相手は一六歳のセリーヌとは六つしか歳のはなれていない二二歳のキャサリン。隣家の七歳のジェイクは両親が離婚寸前で、不安なためなにかとセリーヌに甘えている。ある時セリーヌはジェイクに言う。「ジェイコブ。やっぱり現実を直視した方がいい。家族の暮らしは終わリよ。あんたには、離婚を思いとどまらせるほどの価値がないってわけ」。
これはなにも日本の児童書に限らず、ドイツの物語『屋根にのるレーナ』(ペーター・ヘルトリング 上田真而子訳 偕成社)では、養育権裁判で主人公は、「パムとマムはぼくたちが生まれてくるのをねがっていました。なんべんもそういってました。ぼくたちはパムとマムがのぞんだ子どもです。すくなくとも、まえはそうでした。いまはもうちがいますけど」と言い放ちます。またスェーデンの、『夜行バスにのって』(ウルフ・スタルク
遠藤美紀訳 偕成社)に至っては、「かあさんが家を出て再婚してしまってから、父さんにはシクステンしかいませんでした。だけど、だれかの、たった一つのものでいることは、そんなにかんたんなことではありません」と考える主人公は、このままではいけないと、父さんに新しい伴侶を見つけようと画策を始めるのです。アメリカの『がんばれセリーヌ』(ブロック・コール 戸谷陽子訳 徳間書店)は、父親が再婚した相手は一六歳のセリーヌとは六つしか歳のはなれていない二二歳のキャサリン。隣家の七歳のジェイクは両親が離婚寸前で、不安なためなにかとセリーヌに甘えている。ある時セリーヌはジェイクに言う。「ジェイコブ。やっぱり現実を直視した方がいい。家族の暮らしは終わリよ。あんたには、離婚を思いとどまらせるほどの価値がないってわけ」。これらでは、両親が離婚した子どもは、不幸で可哀想な受け身の存在として捉えられてはおらず、離婚は子どものせいで起こった事態ではないにせよ、そのことによって生じた痛みは、子ども自身が抱えなければならないのだという考えが現れています。子どもの扱い方が変わってきているといってもいいでしょう。
離婚ではありませんが、『ドラゴンといっしょ』(花形みつる 河出書房)では、母親を病気で失った主人公が、六歳年下の弟が心の中に母親代わりにドラゴンを飼い
 始めたのを知り、そんな弟に寄り添って生きようとし、「子ども専門の医療センターで、精神科のあるところ」へ連れて行くべき存在としてしか弟を見られない父親を「自分の父親がここまでアホだとは知らなかった」と思う姿も描かれています。
始めたのを知り、そんな弟に寄り添って生きようとし、「子ども専門の医療センターで、精神科のあるところ」へ連れて行くべき存在としてしか弟を見られない父親を「自分の父親がここまでアホだとは知らなかった」と思う姿も描かれています。一方『バイ・バイ11歳の旅立ち』(岡沢ゆみ ぶんけい)は、主人公の友人真紀の、蒸発した父親の居所を知ったらしい母親がそれを隠しているのに怒った仲良し四人組が夏休み新潟から東京まで彼を訪ねていく物語。「おじさんがいなくなって苦労したのはおばさんだけじゃないんだよ。(略)なのに子どもはかやの外なんて、大人の横暴だよ、身勝手だよ」。「親なんて、ろくなもんじゃない」といった言葉がそこでは見られます。これまでの児童文学なら、そこから始まる物語であっても、様々な出来事を経て最終的には親と子どもに相互理解が成立して、めでたしめでたしとなるのですが、そうはならず、かといって関係が悪化するでなく、また同じ日常が戻り、「わたしたちはときどき、すごーく年寄りみたいな気分で、あの二日間をなつかしく思う」だけなのです。
家族、親子以外の題材も少し見てみましょう。『おとなりは魔女』(赤羽じゅんこ作 文研出版)。隣に引っ越してきた家族は「未婚の母」とその娘。その母親は「髪の毛が爆発して」いて赤く、おへそ丸出しの下着のようなTシャツ姿。ママからみればその非常識ぶりに、あかりと同い年の娘との付き合いを避けるよう暗にほのめかす。が次の日の朝、ルイという娘はあかりに「友だちになれそう」と親しげにいう、というところから始まる、友情物語。でもルイは、私は目立つから学校ではおたがいに知れらぬ振りにしておいたほうが安全だよという。『ひみつの友だち、みつけたよ!』(澤口たま・作 藤枝つう・絵 大日本図書)でも同じで、セキセイインコを逃がして落ち込んでいたため友人にもつれなくしてしまい、そのことがきっかけで孤立してしまうマユを、ある日、これも孤立しているユウタが訪ねてくる。二人は学校では知らぬ振り。そうして孤立したもの同士が学校の外で遊ぶようになる。マユは思う、「そうだ。友だちって、学校の中だけでつくるものじゃないんだね!」
これらでは、学校の捉え方が変化しているのがわかるでしょう。かれらは、学校というシステムをあまり信頼していず、自分たちで処理しようとするのです。
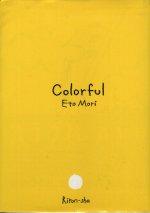 また、『きみの犬です』(令丈ヒロ子 理論社)では、自分が化粧したり笑顔を浮かべるのは、あんたたち男の子をよろこばせるためなんだと、知っている女子高校生が主人公ですし、『カラフル』(森絵都 理論社)だと、自殺した高校生小林真の体を借りて、見知らぬ家族の次男となる主人公が描かれます。
また、『きみの犬です』(令丈ヒロ子 理論社)では、自分が化粧したり笑顔を浮かべるのは、あんたたち男の子をよろこばせるためなんだと、知っている女子高校生が主人公ですし、『カラフル』(森絵都 理論社)だと、自殺した高校生小林真の体を借りて、見知らぬ家族の次男となる主人公が描かれます。ここまでご紹介してきた物語の中の子どもたちは、皆、大人や社会と、自分との距離を測っており、自分の置かれている状況に自覚的であり、なりふり構わず夢中で遊ぶといった、子ども像とは違っているのがお判りでしょう。「なりふり構わず夢中で遊ぶ」姿とは、なにより彼らが大人の保護と支配の基にあり、安心仕切っている姿だと考えれば、これらに描かれる子どもはそうした安心からはズレていると言えます。
その原因は様々でしょうが、一つ挙げるとすれば、今までは大人と子どもを分かつ重要な要素の一つであった、情報量の差が詰まってきたこと。「子どもには関係ないこと」だとか、「まだ子どもだから」といった形で子どもを遠ざけようにも、隠そうする情報を、子どもは別のルートから簡単に得てしまいます(インターネットの普及はますますそれに拍車をかけるに違いありません)。
これらの児童書はそうした時代の子どもたちを、従来の子ども観に押し戻そうとはせず、そのままの姿で受け入れようとしていると言えるでしょう。私たちが最近の子どもは判らないを感じているとしたら、それは、これまでの子ども観のまま、それに現代の子どもを当てはめようとしてしまっているからなのだとも言えます。
そうではなく、今いる子どもこそが、子どもなのだ、と見方を変えることから始めよう! これらの児童書はそう呼びかけているように私は思います。