ルロイ・アンダースン作曲の軽快な曲で、原題はBugler's Holiday。トランペット奏者が、仕事のない休みに思う存分トランペットを演奏するという設定だ、ときいた覚えがある。休みのときぐらい別のことをすればよさそうなものだが、トランペットが好きだからこそ、心ゆくまで吹いたということなのだろう。
トランペット吹きならぬ「本読み」にも同じことがいえる。学期中は、いわゆる読まなければならない本があるため、息抜き用の本には神経をつかう。ときに理性が吹っとんで読みふけり、後悔することになる。でも休暇中ならその心配はなく、食べたり飲んだりしながら読書するのも自由である。(学期中だって、ながら読書はするけれど!)
そこで気をつけたいのが本との「食い合わせ」──食事中に読める本と、そうでない本──である。その観点からすると、もっとも向かない本のひとつは去年訳されたスーザン・プライス『エルフ・ギフト下 裏切りの剣』(金原瑞人訳、ポプラ社、1996/ 2002年7月)だと思う。詳細は省くが、あれほど食欲を減退させる本も珍しいだろう。
読むとおなかがすき、何かしら食べたくなる本もある。これは子どもの本ではないが、池波正太郎の「剣客商売」や「鬼平犯科帳」などがまさにそうだった。池波の手にかかると、どんな食材も料理もひときわおいしそうに感じられるのだが、「蕎麦つゆ」とか、「釜から茹であげた麺」、「種物」といった言葉を見ると麺好きの血が騒ぎ、なにかと口実をもうけては蕎麦屋へ通ったものだ。
*
 そこで今月は、食欲をそそられることで定評があるブライアン・ジェイクスの『小さな戦士マッティメオ』(西郷容子訳、徳間書店、1989 / 2003.02.28)の話から。「レッドウォール年代記」シリーズ3冊目にあたる本だ。
そこで今月は、食欲をそそられることで定評があるブライアン・ジェイクスの『小さな戦士マッティメオ』(西郷容子訳、徳間書店、1989 / 2003.02.28)の話から。「レッドウォール年代記」シリーズ3冊目にあたる本だ。もともと「レッドウォール」は、ジェイクスが朗読奉仕をしていた王立盲学校の生徒に、自作を聞かせたいと思ったことから誕生したそうで、最初は3部作の予定だったとか。翻訳も3冊が出揃ろい、一区切りついたことになる。原書はその後も夏ごとに1冊のペースで出版がつづき、2002年には15冊目が出ている。ジェイクスは年代順には書いていないため、もっとも古い年代の話から読む方法を主張する人もいる。これにたいし、ジェイクス公認の「レッドウォール・ホームページ」管理者デイヴ・リンジーは、出版順に読むことを勧めている。シリーズが継続中で年代記の全貌が把握できない以上、今の時点ではリンジーの主張のほうに理があると思う。
この3冊に限っていえば、2冊目『モスフラワーの森』(1988 / 2001.12.31)がもっとも古く、レッドウォール修道院ができる以前のマーティンの時代をあつかっている。3冊目は、時間的にはマサイアスが活躍した1冊目『勇者の剣』(1986 /1999.07.31)の続きで、マサイアスのその後を伝えながら、息子の成長も描いている。ピアズ・アンソニーが「ザンス」シリーズでおこなっているように、ジェイクスも主人公をつぎつぎにバトンタッチさせている。それによって同種の冒険を繰り返し書けるし、各巻のなかでの主人公の成長も描きやすくなるからだろう。
レッドウォールのシリーズには、宴会や食物の描写が多い。今回も、修道院で夏至の祭りのために準備をしている場面と、マサイアスに逆恨みしているキツネのスレイガー一味の悪巧みの場面とが交互に進行し、宴会にはいる。潜入したスレイガーたちはマッティメオ(マサイアスとコーンフラワーの間に生まれた息子)を含むレッドウォールの子どもたちをさらい、奴隷として働かせるために南へ連れて行く。マサイアスは子どもをさらわれたほかの動物たちと追跡の旅に出かける。彼らが留守のあいだに、ミヤマガラス族が修道院の乗っ取りをたくらみ、留守部隊との攻防が繰り広げられる。物語はこれら3つのプロットが交互に進み、子どもたちの救出を果たしたマサイアスらの一行が、秋にもどり、祝宴となる。
主人公の出発から帰還までという大きな流れは、ジェイクスがホメロスの叙事詩にならったものだろう。同時に、同じくホメロスを意識したグレアムの『たのしい川べ』の影響も忘れることはできない。(そのほかアダムズ『ウォーターシップダウンのうさぎたち』やC・S・ルイス「ナルニア国物語」からも影響を受けている。)
グレアムが描く動物たちのピクニックには、コールドハムやコールドチキンが出てきたが、善良なレッドウォールの住人が食べるのは、もっぱら野菜と果実が中心で、それにチーズなどの乳製品と魚料理などが加わる。いっぽうずる賢い動物はこれらの食物も食べるが、ほかの動物を捕食するか、搾取することで食物を得ようとする。そこでネズミ、スズメ、アナグマ、リス、モグラ、カワウソなどが「善」の動物、キツネ、イタチ、ヘビ、ドブネズミなどが「悪」の動物となる。前述のホームページには、「どういう基準で動物の善悪を区分したのか」という問いに、ジェイクスの「ヨーロッパの伝承などに見られる伝統的区分にしたがった」という回答がのっていた。
さて、『戦士マッティメオ』の9章から食卓風景を書きだしてみよう。
サラダは十二種類。手に入るかぎりの夏野菜を使ってある。赤かぶに二十日大根、何種類ものレタスにういきょう、たんぽぽにトマト、小たまねぎににんじん、長ねぎにとうもろこしなどなど。(中略)サラダのとなりには、三角形に切りわけた赤や黄色や白の円盤チーズに、木の実や香草やりんごの角切りをそえて盛りあわせてあった。食卓のそこかしこにパンが置いてある。けし粒やごまをてっぺんにちりばめた胚芽入りの丸パン、こんがりとぱりぱりに焼けたコッペパン、麦の束をかたどったパンは収穫が終わったばかりの早の小麦で焼いてあり、ほかに紅茶パン、木の実のパン、香辛料のきいたパン、赤ちゃんのためのやわらかな花形のパンまであった。(中略)それからデザートには、いろいろな甘いお菓子が並んだ。きいちご味やブルーベリー味のバター入りパン、あかふさすぐりのゼリー、特製のレッドウォール院長ケーキ、フルーツケーキ、卵白と粉砂糖を練りあわせた砂糖衣で飾ったケーキ、堅焼きビスケット… (以下略;74ページ)
よく見ると、ごちそうの種類をたくさん並べることで豊かなイメージが生まれているようだ。作者ジェイクスはどこかで、食べ物へのこだわりの根底に第二次大戦中に経験した空腹感があると述べていたが、その気持ちはわかる気がする。
*
じつは2巻『モスフラワーの森』で印象に残ったのは、作中に蔓延する飢餓感と欠乏感とであった。
この巻は、ヤマネコの一族がモスフラワーの森の砦を拠点とし、圧政をしいているところで幕をあける。主人公のネズミ・マーティンは旅の途中で森を通りかかり、動物たちの窮状を知る。アナグマやリス、ハリネズミやモグラらが戦う一方、マーティンは援軍を求めて探索の旅をし、最終的に一同で敵を倒して自由な暮らしを取り戻す。その後修道院が建てられ、冒険が語り継がれていく様子が、エピローグで示されている。
物語の冒頭には、税と称して越冬用の食料を根こそぎ奪っていくヤマネコの手下の非道な仕打ちが描かれている。『ライオンと魔女』の白い魔女とその手下たちを連想させる場面だが、ここで注目したいのは、すでに殺されるか森を脱出した住人が多く、砦の軍隊を維持しつづける税(食料)を集めるのが難しくなっていたことである。
運悪く捕まったネズミのマーティンは、地下の牢屋にいれられ、あてがわれるのはパンと水だけとなる。数ヶ月後、彼のいる牢にネズミのガーンフが加わったとき、マーティンは「顔はげっそりとやつれ、体もやせほそっていた」。そこでガーンフが食料庫から盗んできたチーズとワインを上着から取りだすと、腹をすかせたマーティンは、チーズをがつがつ食べ、ワインをがぶ飲みして、彼にたしなめられている。マーティンはガーンフ救出作戦のおかげでいっしょに牢から脱出できる。以後も探索の途中で食糧不足に悩む時期をのぞき、いつも仲間が何かしら調達してくれるため食べ物で悩むことはあまりない。
いっぽう、当初豊富だった砦の食料庫は、倉庫番らの盗み食いもあり、また手下の人数の多さからだんだん減っていく。そのうえ食料の割り当てにも不公平があり、兵士たちの不平はつのり、士気はあがらない。作者はこれでもかというように彼らのみじめな生活を描いている。手下たちは、たがいに足をひっぱりあい、あげくに命を落としていく。ツアーミナのもとに、新しい将校が有能な部下と食料持参で加わり、形勢は多少持ち直したかに見る。だが、最終的には森の住人たちによるゲリラ活動がまさっており、ツアーミナ
は命を落とし、森は解放される。
このシリーズでは、中心となるヒーローと、大物敵対者の葛藤が筋を動かす。そのため大物敵対者は、途中の困難をものともせず生き延び、大詰めでかろうじて倒されることになる。つまり、物語をひっぱるために欠かせない大事な、影の主人公なのである。1巻ではドブネズミのクルーニーが、2巻ではヤマネコのツアーミナが、3巻ではキツネのスレイガーがそれにあたる。
そこでもう一度、2巻のツアーミナを見てみよう。彼女は父王を毒殺し、弟を追い払って王の座をものにした野心家である。だが、強欲と猜疑心の強さから誰も信頼できず、妄想につきまとわれて苦しむ。仲間を遠ざけ、孤立をえらんだツアーミナだが、孤立すればするほど、孤独感がつのればつのるほど、なおいっそう欠乏感におそわれ、いっそう強欲になる。まさに悪循環である。それにたいし、モスフラワーやレッドウォールの生き物たちはたがいに協力を惜しまず、正直かつ誠実をモットーとしており、孤独とは無縁なのだ。このあたりに、作者の主張があることは容易に見て取れるだろう。
なんだか食事の話からだいぶ逸れてしまったが、寄り道ついでにこのシリーズへの不満を述べておきたい。ジェイクスは「言葉で絵を描く」ことに力をいれ、パターンを利用しながらも謎解きなどで読者をひきつける工夫をしている。だからこれが、人気シリーズになったのはうなずけるのだが、善悪の戦いというテーマには厄介な点もあると思う。もちろんレッドウォール修道院は平和主義をモットーとしているため、襲撃されても相手を殺さず追い払うのが基本だ。でも修道院の外では事情ががらりと変わり、敵と応戦するあいだに累々と死者の山が築かれていく。怖いのは、「善」の動物に肩入れして読むうちに、「悪」が殺されることを当然と思い、彼らが倒されるのを待ち受けていることだ。3巻でも後半は大殺戮となるので、感覚が麻痺しそうになった。確かにレッドウォール側に即すれば彼らの言い分が正しい…と思えるのだが、こういうふうに感覚が鈍磨するのは避けたいものだ。それとも目下の世界情勢に影響され、わたしが過剰反応しているのだろうか。
もうひとつ気になるのが男性優位の構図である。まえに某所で1冊目を男性中心だと批判したが、つづく2冊でも、それは解消されていない。
レッドウォールは修道院だから、料理をするのは男性修道士であった。だがそこに森の住民が避難する事態になると、性別役割分業が顕著になる。戦いに出かけるのは男性で、子どもや老人とともに留守を守り怪我人の手当てをするのは女性(と中性的な修道士たち)の仕事になる。つまり伝統的に女性の役割だった子育てと看護が、レッドウォールの世界で踏襲されているのだ。そこでコーンフラワーが「母親」であることが強調され、修道女のメイがすぐれた看護の腕をもつと描かれる。ほかに女性で印象的な顔ぶれをさがすと、
ツアーミナに代表されるような悪漢役か、たくましいアナグマのコンスタンスぐらいだ。(ただしコンスタンスは「レッドウォールの母」とされている。)そのほか3巻では、コーンフラワーが策略にとんだところを見せ(1巻でもその片鱗が見られた)、留守部隊のなかでは光っている。だが最終的には彼女も院長の指図に従う姿勢をみせている。だから全体として女性は補助的な役割なのである。ジェイクスは未訳の4巻目ではメスネズミを主役にしているようだが、最初の3冊に関する限り、フェミニストには居心地の悪いシリーズなのである。
*

去年、ジェイクスの別のシリーズが邦訳紹介された。その1冊目『幽霊船から来た少年』(酒井洋子訳、早川書房、2001 / 2002.12.10)は、「さまよえるオランダ人」の伝説を下敷きにして、同船に乗り合わせた孤児のオランダ少年ネブと黒犬の数奇な運命を語る本で、海洋冒険小説、幽霊物語、歴史小説、さらに謎解きの本としても楽しむことができるだろう。全体は3部構成になっていて、第1部でネブの視点から、伝説の船「フライング・ダッチマン号」が呪いを受けるにいたる事情を明かす。その後ネブと犬は天使によって永遠の命を与えられ、善をおこなう放浪の旅に入る。第3部はそんな善行のひとつが19世紀末のイギリスの村を舞台に展開されている。1部では言葉がしゃべれなかったネブは、2部からは言葉が話せるようになり、ネブと犬もたがいに言葉が通じるようになる。動物ファンタジーを書いてきたジェイクスが設定も新たに展開させる、楽しみなファンタジーである。
*
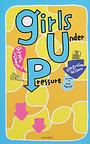 ジャクリーン・ウィルソンの『ガールズ アンダー プレッシャー』(尾高薫訳、理論社、1998 / 2003.02)が出た。『ガールズ イン ラブ』(尾高薫訳、理論社、1997/2002.07)に続く中学生の少女3人組の物語である。
ジャクリーン・ウィルソンの『ガールズ アンダー プレッシャー』(尾高薫訳、理論社、1998 / 2003.02)が出た。『ガールズ イン ラブ』(尾高薫訳、理論社、1997/2002.07)に続く中学生の少女3人組の物語である。三角形は図形としては安定がよいが、3人組というのは、そのうちの一人が疎外感をもちやすく、友情を保つのはなかなか難しいものである。前作は恋愛がテーマで、さっさと恋人をつくってしまうマグダとナディーンにつられ、主人公のエリーも休暇中に会った文通相手ダンを恋人だと吹聴する。三者三様の恋の展開に、父が再婚し義理の母と弟がいるエリーの家庭の事情も加わり、一人称で騒々しく語られる話であった。
2作目の今回は、スタイルがよく、モデルコンテストにも応募できる二人を見て、エリーがやせようと一念発起し、食事を抜く「ダイエット」が話の中心となっている。エリーはもっとやせなくてはと思うのだが、まわりではエリーのやせ方を心配している。だが彼らの忠告も「やせた」という言葉も、思いつめているエリーの耳には届かない。とはいえ、拒食症が進み、ついには入院にいたるクラスメートを目にすれば、エリーならずともその異常性に気づくことになる。エリーはとうとう危険な「ダイエット」をやめ、周囲をほっとさせる。
ウィルソンはストーリーテラーとして実績のある作家だが、今回とくに巧妙だと思ったのが、物語中で一度も具体的にエリーの体重を述べなかった点である。これはおそらく読者への影響を考慮したものだろうが、大正解である。エリーは、ほっそりして見える親友ナディーンの体重を聞いたとき、自分とあまり違わないと感想を漏らすが、この場面ですら具体的な数字は一切示されていない。
それにしても、ナディーンのように世の中にはいくら食べても太らない(ように思える)人もいる一方、食べた分がそのまま体重に反映する(運の悪い?)人もいる。わたしもどちらかというと後者に属する。それなのにエリーが必死に食べまいとする部分を読みながらおやつのスナックを食べていると、いかにも自分が意志薄弱な気がして後ろめたくなった。ただしこの作品は、ダイエットの話にことよせ、自分が何かを得意とし、自信をもてば、スタイルだけに気をとられずにすむという、ごくあたりまえのことを少女たちにアピールしている本である。ウィルソンは、それを軽いのりで読ませる話にしている。「少女小説」についてはもっと述べたいところだが、レッドウォールに思わぬ時間をとられ、尻切れトンボとなった。いずれどこかでまとめて述べられたらと思う。ではまた。( 西村醇子)