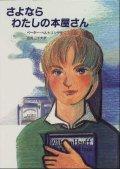 イェッテはベルリンに住む十二歳の少女。両親は離婚し、イェッテは新聞記者をしている母親のカローラと二人で、母と娘の新しい生き方を模索している。ある日、イェッテはカローラの用事で近所の本屋さんを訪ね、そこの二人の老人と知り合う。空想力豊かなイェッテは、本好きな本屋のトプフさんとプレシュケさんと意気投合する。この二人を通して、イェッテの前に新しい世界の扉が開く。本の世界とナチス時代の戦争の世界の扉である。
イェッテはベルリンに住む十二歳の少女。両親は離婚し、イェッテは新聞記者をしている母親のカローラと二人で、母と娘の新しい生き方を模索している。ある日、イェッテはカローラの用事で近所の本屋さんを訪ね、そこの二人の老人と知り合う。空想力豊かなイェッテは、本好きな本屋のトプフさんとプレシュケさんと意気投合する。この二人を通して、イェッテの前に新しい世界の扉が開く。本の世界とナチス時代の戦争の世界の扉である。クリスマス前の土曜の午後、トプフさんとプレシュケさんがイェッテに、本屋でハウフ童話の影絵芝居を演じてくれる。クリスマスプレゼントとも思える素敵な午後は、二人の本屋さんにイェッテ虐待の疑いがかけられ、悲しい結末をむかえることになる。
まず本書に見られる社会問題としては、両親が離婚した後の母と娘の関係と、子どもに対する性的虐待の問題である。イェッテは父親のいなくなった寂しさに時にはくじけそうになりながらも、父親のことは口にださずカローラと前向きに生きている。カローラはカローラでイェッテにとって母親と友達の両方でありたいとして自分をカローラと名前で呼ばせている。イェッテは友達としてのカローラに慣れてはきたが、カローラの恋人には反感を抱いている。
イェッテと二人の本屋さんの関係が誤解を招いた子どもに対する性的虐待の問題は、日本ではあまりなじみがなく子どもの本にこんな問題がと奇異に感じられるかもしれないが、欧米ではそれだけ深刻な問題で、青少年局の対応もまわりの大人達の反応も納得のいくものなのである。ただ、これによって壊れてしまったイェッテと本屋さんの関係やイェッテの心の傷や悲しみは如何ともしがたい。
この現実の問題を下敷きに本書には別の世界が展開する。イェッテの空想の世界と本の世界とナチスの時代とである。イェッテの空想の世界とは、新聞で見た記事からとっさに思いついた気球に乗る話と、カローラの服や帽子を使いイェッテとカローラが様々な人物に変身する仮装ごっこである。
本の世界の始まりは、イェッテがトプフさんにもう一人のイェッテの話をしてもらうところからである。もう一人のイェッテとはトプフさんが大好きな小説の女主人公で、ここからイェッテはトプフさんと「別の世界へと旅をする。」
二番目はトム・ソーヤーである。トプフさんは、子ども時代にトム・ソーヤーごっこをしたベルリン郊外へイェッテを連れていく。三番目は、カール・マイの『砂漠を突っ切って』。トプフさんとプレシュケさんは時々この砂漠へでかける(二人して砂漠の場面を演じる)。この場面が二人を生涯の友にしたのだ。最後は二人がイェッテに影絵芝居を演じてくれたハウフ童話の「小人のムック」である。あらぬ疑いをかけられ三人の本の世界はなくなってしまったけれど、イェッテの二人に宛てた手紙も示しているように、イェッテはトプフさんとプレシュケさん、二人に教えられた本の世界をけっして忘れない。
ナチスの時代は、本の世界と密接に結びついている。イェッテは、トプフさんに連れられていったベルリン郊外で、トプフさんにナチス時代の話を聞く。トププさんが友達とトム・ソーヤーごっこをしていた時にナチスの突撃隊員がした殺人を目撃したこと、その友達がユダヤ人だったためにたどった悲惨な運命と、戦争の後で起こった小さな奇跡とである。
以上がイェッテが体験する別世界だが、なかでも印象深いのは本の世界である。ナチスの時代は、『ぼくは松葉杖のおじさんに会った』や『家出する少年』でも取り上げられているテーマであり、本の世界と共に、ヘルトリングの少年時代の体験を反映したものと思われる。本の世界を中心に様々の世界や問題を扱った本書はヘルトリングの思い入れが一杯につまった一冊なのである。(森恵子)
図書新聞1997年2月1日