育つことをやめた子どもが、「育ちなおす」きっかけをつかみとり、やがて自立していくには何が必要か。
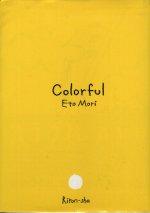 『カラフル』を読むと、そのことがよくわかる。
『カラフル』を読むと、そのことがよくわかる。こうだ。
死んだはずの「ぼく」の魂が、ゆらゆらと漂っていると、突然、プラプラと名乗る天使から、「おめでとうございます」と声をかけられ、そして、抽選に当たったから、小林真という睡眠薬自殺をした少年のからだを借りて、その少年の家でホームステイしながら修
行をつとめなければならないと半ば強要される、というところからこの物語ははじまる(朝日新聞朝刊連載「子どもの本棚」98・9で、「コメディーだが、人生の意味を切実に問う」と紹介されている)。
真は、14歳(中3)の少年で、ある日、わずか一日のあいだに耐えかねないほどの「悲劇」に遭遇し、それが引き金となって自殺を図ったのだが、その「悲劇」とは、
中年男とラブホテルに入る初恋の君 不倫する母親に、自分さえよければそれでいい父親 さらには、通販で買ったシークレットブーツのことで兄にさんざんからかわれる、というものだった。
天使のプラプラから与えられた情報は、真をして次のような思いにさせるのだった。
「平凡であたたかい家庭だと思ったら、じつは悪魔の巣窟みたいなところで、やさしくて愛情ぶかいはずの家族たちは、そろいもそろってろくでもない本性を隠しもっていた。役者ぞろいの仮面家族」
(10)
しかし、「ぼく」は、「母親の不倫に対する生理的な嫌悪感だけは、どうしてもクリアできない障害として残っ」たものの、次第に、家族に対して心を開いていくようになる。
そんなある日、父親に誘われて渓流釣りに出かける。そして、案の上、「ぼく」は、「本物の真がきくべきだった」話を、父親から聞かされる(この父親、なぜか、映画「釣りバカ」の西田敏行を連想させる。そのあたりは、作者の狙い通りなのかもしれない。とすると、『超・ハーモニー』の父親は、佐野史郎あたりか。田中邦衛では老けすぎだろう。余談だが、TVドラマを見ていると、中年の役者は゛いい人゛ばかりで、悪役がいないのはなんとも情けない)。
「ぼく」が、「今がよければ、過去のことはもういいわけ?」と聞いたのに対して、父親はこんなふうに答えたのだ。
「そりゃあ、うらんでいたさ」
長い沈黙のあとのことだ。
そして、「いくら今がよくたって、悲惨な過去が消えるわけじゃない」と、長いあいだ胸に秘めていた思いを話しはじめ、「そんな自分にいやけがさしたこともある」と結ぶ。しかし、と父親はいう。真が生き返った瞬間、そんな感情はすべて一瞬のうちにふきとんでしまった、と。
「あ」
ずきんとした。
「ぼく」のほうが動いたのかもしれない。あるいは、父親のほうかもしれない。しかし、たしかに、ずれが修復していく実感はあった。向き合えるかもしれない、「ぼく」は、そんな手ごたえを感じたはずだ。
その夜、「ぼく」は、枕を濡らす。「泣いているのか」というプラプラに、「ぼく」は、「真の涙だ」と答える。
翌日から、「ぼく」は、父親をさけるのをやめる。
(11)
わが子に向かって、「まだまだ父さんの人生もすてたもんじゃない」などといって胸をはってみせる父親なんてそうはいない。だいいち、上司たちがいっせいに検挙され、残った重役も責任をとって総辞職したために、平から部長に一気に三段跳びの昇進をしたその日、玄関から居間まで、でんぐりがえしをしながら入ってきて、子どもたちの顔を見るなり、いきなり抱きついてキスをするなんていう父親もなかなかいない。それでいて、この父親、満員電車でも笑顔をくずさず、年よりがいればまっさきに席をゆずりそうなタイプに見えるのだ。そのくせ、会社の経営をめぐって口を出したがために窓際に追いやられ、二年間、死人のように過ごすという苦労も味わっている。しかも、昔は女ぐせが悪くて、母親は、浮気相手の女の人から別れてくれとつめよられたことが三回もあるのだという。かと思うと、妻が思い詰めているというのも知らずに、パワーみなぎる救世主と思い込んでいるという単純なところもある。
まあ、なんといったらいいのか、文字どおり「カラフル」な父親ではないか。ここには、もはや「いい悪い」など存在しない。いや、もっといえば、実にけしからん、悪いやつなのだが、それを突き破った世界に行ってしまっている。
だが、そのことと、わが子が生き返った瞬間すべてが一瞬にふきとんだということとは矛盾しない。
チョーシよすぎないでもないが、わが子とちゃんと向かい合おうとする父親。「まじめであることが人生でいちばん、大事」の一点張りで、そこから外れている者を「異分子」として排除しようとかかる父親。
愛されることの困難がどちらにあるかは、いうまでもないだろう。
(12)
前後するが、父親と釣りに出かけたその夜、もう一つの出来事が起きる。「満の声を、死んだ真にきかせてやりたかった……」と思うやりとりが二人のあいだで交わされるのだ。
「本物の真がきくべきだった」父の話。「とりかえしのつかない誤解をこの世に残したまま」死んでしまうことの不幸を嘆かわずにはいられない「満の声」。
このことに加え、それ以前に、母親から手渡された手紙の最後に書かれていた、
「私は、あなたの中にある普通の部分も、非凡な部分も、どちら も心から愛しています」のことばによって、まだ、ボタンを押したことにはならないだろうが、リセットボタンを探る手が忙しく動きはじめたことは疑いない。
また、母親に対する嫌悪感がクリアできないでいることも、実は、「ぼく」が真その人であったということで「ははあん」と合点できる仕掛になっているし、その嫌悪感も、やがて時間が解決してくれることになっている。
実は、真は、もっと早くに自殺していていい子どもだった。それが、14歳まで生きてこれたのは、母親のおかげである。絵という非凡な才能を発見しその能力を伸ばしてあげようとしたのは、母親である。そして、絵があったからこそ、真は14歳まで生きてこれたのだった。
そういう意味では、母親のことを「唯一のぼくの理解者=信じられる人」と思い込んでいた分、かんたんには許すことがきなかったのである(ただ、「信じていたのに裏切られた」という出し方は、あまりに一方的すぎるし、他者との向い合い方に弱さを感じる。この弱さが、母親の描写が風俗に走りすぎているような、物足りなさといらだちを呼びおこす)。